 全国32万人の就労人口が20年で17万人まで減った水産業。東日本大震災が追い打ちをかけるなか、宮城県石巻市にあるフィッシャーマン・ジャパンは「担い手育成事業」と「水産物販売事業」を2本柱に、復興を超えた革新的な産業構築へ挑戦を続けている。
全国32万人の就労人口が20年で17万人まで減った水産業。東日本大震災が追い打ちをかけるなか、宮城県石巻市にあるフィッシャーマン・ジャパンは「担い手育成事業」と「水産物販売事業」を2本柱に、復興を超えた革新的な産業構築へ挑戦を続けている。
被災地で進む新しい挑戦や地域の魅力を特集記事で紹介します。

福島第一原発の事故で全村避難を余儀なくされた福島県川内村。一時は人口ゼロとなった村には、避難解除後の今も震災前の賑わいは戻っていない。ふるさとを活性化するために、自分に何ができるのか。高校卒業後村を離れ、震災を機に約20年ぶりに帰村した渡辺正さんは、様々な困難に遭遇しつつ、少しずつアイデアを形にしていく。

僕は震災前、石巻という町に不満とあきらめを抱いていた。徐々に広がっていく商店街のシャッター通り、閉鎖的な人間関係、古いしがらみ、力をもつ一部の人たちだけで決める物事の進め方、そんな地域に対して若者が抱く将来への閉塞感…。震災は確かに大きなダメージだったけど、単に震災前の状態に戻すだけでは不十分だった。(2018年1月19日掲載)
2015年4月に創刊した「こうふく通信」は、2018年2月には第12号を発行する。「こうふく通信」は、福島の風評被害払拭への貢献と編集部の高校生の成長という目的に向かって、どのように前進しているのだろうか。


僕が東北に根を張り、「漁業に革命を起こす」と今も走り続ける動機と原動力は、どこにあるのか。僕がこの世に命を授かった「3月11日」という日、愛する弟の死、大好きな日本の原風景や地方衰退への危機感。僕自身のルーツを辿っていくと、それはどこか運命的なものでもあるような気がしている。(2018年1月5日掲載)
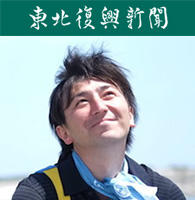
海へ出て魚を獲るだけだった漁師から、水産加工品の開発や販売など2次・3次産業にも手を広げるようになったこと。それが、震災前にはなかった大きな変化だ。
震災と原発事故がある前まで、福島県沿岸地域の漁業は沿岸・沖合漁業としては全国屈指の水揚量を誇り、他の地域に比べて若い漁師も育つ「稼げる」漁場だった。(2017年12月26日掲載)
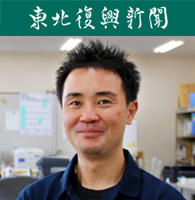
NPOなどの「ソーシャル業界」で、ごはんを食べる人が何十倍にも増えた。このことが、震災後の岩手をはじめとする東北で生まれた、目に見える大きな変化だろう。
それまでは、地域のコミュニティやまちづくりなどに関わるプレイヤーは高齢の世代が中心だったし、僕らの同世代でもソーシャル専業で生計を立てている人はごく一部に限られていた。(2017年12月22日掲載)

震災からの約6年間、ずっと考え続けていたことがある。それは、「復興」とは何か、どういう状態になれば復興したと言えるのか?ということだった。僕らは5つの指標で「復興」を定義することにした。(2017年12月19日掲載)


