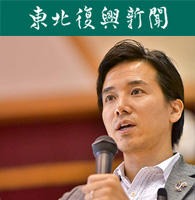
震災後の約7年間、歴史や社会の変化をこれほどダイナミックに肌で触れる感覚を味わうのは、初めてだ。2011年3月12日、福島第一原発1号機が爆発した映像を目にした瞬間、私の中で何かがはじけた。すぐにそのとき働いていたマッキンゼーを休職し、災害支援を行うNPOと契約して仙台へ向かった。(2018年2月7日掲載)
被災地で進む新しい挑戦や地域の魅力を特集記事で紹介します。
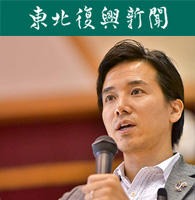
震災後の約7年間、歴史や社会の変化をこれほどダイナミックに肌で触れる感覚を味わうのは、初めてだ。2011年3月12日、福島第一原発1号機が爆発した映像を目にした瞬間、私の中で何かがはじけた。すぐにそのとき働いていたマッキンゼーを休職し、災害支援を行うNPOと契約して仙台へ向かった。(2018年2月7日掲載)
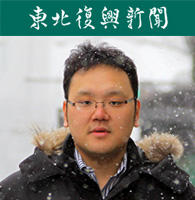
数多くの変革者やチャレンジャーが生まれた。それが、震災後の東北で起きたポジティブな変化だ。被災地には、従来の経済合理性ではないものに価値や生きがいを見出し、社会や地域のために活動する人が東北内外からたくさん押し寄せた。さらに、そうした挑戦者を支えたり、あるいは触発されて自ら起業するようなプレイヤーも生まれた。(2018年2月4日掲載)
 東日本大震災で、甚大な被害に見舞われた宮城県女川町(おながわちょう)。津波が町を呑み込み、一般家屋の約7割が全半壊、死者、行方不明者は人口の1割近い827名に及んだ。その復興、まちづくり、人づくりに取り組むNPO法人のひとつが、小松洋介さんの立ち上げた「アスヘノキボウ」である。
東日本大震災で、甚大な被害に見舞われた宮城県女川町(おながわちょう)。津波が町を呑み込み、一般家屋の約7割が全半壊、死者、行方不明者は人口の1割近い827名に及んだ。その復興、まちづくり、人づくりに取り組むNPO法人のひとつが、小松洋介さんの立ち上げた「アスヘノキボウ」である。
 東日本大震災で、甚大な被害に見舞われた宮城県女川町(おながわちょう)。津波が町を呑み込み、一般家屋の約7割が全半壊、死者、行方不明者は人口の1割近い827名に及んだ。その復興、まちづくり、人づくりに取り組むNPO法人のひとつが、小松洋介さんの立ち上げた「アスヘノキボウ」である。
東日本大震災で、甚大な被害に見舞われた宮城県女川町(おながわちょう)。津波が町を呑み込み、一般家屋の約7割が全半壊、死者、行方不明者は人口の1割近い827名に及んだ。その復興、まちづくり、人づくりに取り組むNPO法人のひとつが、小松洋介さんの立ち上げた「アスヘノキボウ」である。
 災害とそれに続く復旧・復興支援活動は、多くの教訓を残す。それを体系的に整理し記録、公開するのが、IT企業、グーグルによるプロジェクト「未来への学び」だ。ばらばらな団体・個人の経験を共有の財産にする試みは、IT時代の語り継ぎといえるだろう。
災害とそれに続く復旧・復興支援活動は、多くの教訓を残す。それを体系的に整理し記録、公開するのが、IT企業、グーグルによるプロジェクト「未来への学び」だ。ばらばらな団体・個人の経験を共有の財産にする試みは、IT時代の語り継ぎといえるだろう。

ビールとワインの空瓶が部屋中に転がり、テーブルの上にはタバコの灰が散らばっている。あれは、震災後1年のとき、私たちが現地で自らの支援がニーズに即しているか、課題解決となっているかを検証するために家庭訪問をしていた。そこで目に飛び込んできた光景が、どうしても忘れられない。(2018年1月31日掲載)
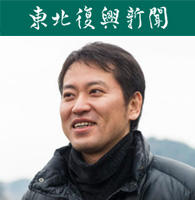
小学校には、保健係や図書係などの様々な「係」がある。社会を「学校の教室」という小さな単位に例えた場合、あなたは「何係」だろうか?震災後、多くの個人や組織に芽生えたのは、そうした社会におけるそれぞれの「役割の再定義」だったのではないか。(2018年1月29日掲載)
 災害とそれに続く復旧・復興支援活動は、多くの教訓を残す。それを体系的に整理し記録、公開するのが、IT企業、グーグルによるプロジェクト「未来への学び」だ。ばらばらな団体・個人の経験を共有の財産にする試みは、IT時代の語り継ぎといえるだろう。
災害とそれに続く復旧・復興支援活動は、多くの教訓を残す。それを体系的に整理し記録、公開するのが、IT企業、グーグルによるプロジェクト「未来への学び」だ。ばらばらな団体・個人の経験を共有の財産にする試みは、IT時代の語り継ぎといえるだろう。
 2014年にフィッシャーマン・ジャパンが走り出してから、イベントへの出店や、プロモーション活動への参加などさまざまな誘いがあったが、イベントへ出店してみても、なかなかそれが継続的な活動に繋がらない。事業として継続するための具体的なプランが必要なのではないか。
2014年にフィッシャーマン・ジャパンが走り出してから、イベントへの出店や、プロモーション活動への参加などさまざまな誘いがあったが、イベントへ出店してみても、なかなかそれが継続的な活動に繋がらない。事業として継続するための具体的なプランが必要なのではないか。
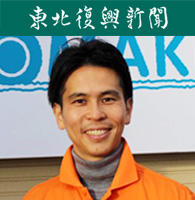
社会の「振り子」が戻り始めた。震災後の変化を一言で言うならこういうことだろうか。これまでの価値観が大きく揺さぶられ、生きる意味を見つめ直す種火のようなものが、個々の心の中で燃え出した。それは、行き過ぎた資本主義に対する「本当にこのままでいいのか?」という警告と揺り戻しだったのではないか。(2018年1月24日掲載)