
「逃げろー!」。突如、大きな声が響き渡った。紙芝居をしながら大声を出す男性の一挙手一投足に、子どもたちが息を飲むように見入っている。これは、大船渡津波伝承館が実施している津波の脅威と避難の大切さを伝える活動の一幕だ。
被災地で進む新しい挑戦や地域の魅力を特集記事で紹介します。

「逃げろー!」。突如、大きな声が響き渡った。紙芝居をしながら大声を出す男性の一挙手一投足に、子どもたちが息を飲むように見入っている。これは、大船渡津波伝承館が実施している津波の脅威と避難の大切さを伝える活動の一幕だ。

巨大な濁流が建物を次々となぎ倒し、そこにあったはずの町が跡形もなく飲み込まれていく。震災発生当日の2011年3月11日に、大船渡市で撮影された映像だ。JR大船渡駅前にある大船渡市防災観光交流センターでは、当時の被災の様子を伝えるこうした貴重な映像や写真が今も展示され、津波の恐怖や防災の重要性を後世につなごうとしている。

遠野まごころネットの中心的な活動となっている、ワインをはじめとする6次産業化プロジェクトや商品開発。ノウハウがない中で見出した打開策の1つが、民間企業のCSR活動と連携させる手法だった。

一帯が色鮮やかな緑色に光り輝く農園で、手足が不自由な障害者たちが黙々と苗を植えたり、懸命に収穫作業を行っている。震災後に発足した遠野まごころネットが、同県大槌町と釜石市、遠野市に切り拓いた農園の風景だ。

2011年3月11日を境に、多くの個人や企業が、「to do」(何をすべきか)ではなく「to be」(どうあるべきか)を意識し、これまでの規範や枠組みを取り払って行動する姿が目立つようになった。(2018年3月21日掲載)
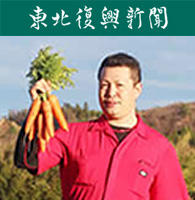
俺が8代続く小さな農園を継いだのは2003年、21歳のときだった。伝統を引き継ぎつつ、俺の代で新しい農業のスタイルをつくりたい。そう思い、農業高校・大学時代から学んできた無農薬・無化学肥料の自然農法を導入した。正直言って、当時は今ほど頑張らなくても、野菜はそれなりに売れ、それなりに稼げた。(2018年3月20日掲載)
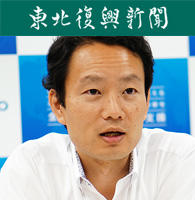
360度、見渡す限り瓦礫の山。自然に元通りに戻ることはなく、誰かに任せておけば片付くものでもない。「何かしないと」「自分が動かなければいけない」。目撃者の心の中に、本能的にスイッチが入った。それは何も、東北にいた人たちだけではない。テレビであの惨状を目の当たりにした日本中の人たちが、当事者意識を呼び覚まし、心を起動させた瞬間だった。(2018年3月19日掲載)

「一緒に東北でやらないか」。2012年秋、上司から突然かかってきた電話。当時、私はストリートビューの撮影で西日本エリアを担当していた。私で大丈夫だろうか。正直、戸惑いもあったが、少しでも役に立てることがあれば。そんな思いで、復興支援のチームに加わった。月の半分を東北の現場で過ごす激動の日々は、そうして始まった。(2018年3月17日掲載)

早いもので、あれからもう7年。家がないときは仮設住宅を急いでつくって、次に完成したのは復興住宅。今度はまたゼロから住民コミュニティを立て直す。課題が次々と消えては現れる。果てしない課題との対話は、これからも長く続くのだろう。(2018年3月15日掲載)

あの震災の後、三陸沿岸部には歴史が始まって以来の瞬間最大交流人口が生まれたのではないか。国内外から多くの人、しかも様々な立場や年齢、スキルをもった人が一斉に押し寄せ、復興や社会課題解決の実験場となり、あちこちで様々な変化が起きている。(2018年3月14日掲載)