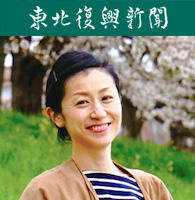
「放射能って何?」「死ぬかもしれないの?」。原発事故や放射線量に関する得体の知れない言葉が飛び交い、不安と混乱が渦巻く。「これはフィクションなのでは?」。事故からの数カ月間は、まるで映画やドラマの世界にいるみたいだった。(2018年3月11日掲載)
被災地で進む新しい挑戦や地域の魅力を特集記事で紹介します。
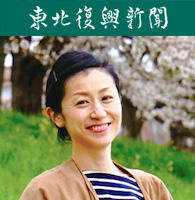
「放射能って何?」「死ぬかもしれないの?」。原発事故や放射線量に関する得体の知れない言葉が飛び交い、不安と混乱が渦巻く。「これはフィクションなのでは?」。事故からの数カ月間は、まるで映画やドラマの世界にいるみたいだった。(2018年3月11日掲載)

「市民協働」のステージが変わり、その動きが飛躍的に進展した。あの震災を境に生じた社会、そして東北の変化を表すとき、私はこのことを最も強く感じる。
震災前に語られていた「市民協働」は多くの場合、その言葉とは裏腹に、あくまで地域づくりの主体は行政が担い、市民はそれに協力する。そういった考え方だったように思う。(2018年3月10日掲載)
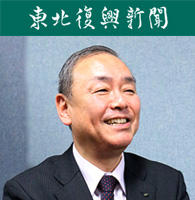
東北は、キリンにとって最大の勉強の場所だ。現地の人たちからよく「ありがとう」と感謝されるが、震災復興の活動で一番勉強させてもらっているのは、間違いなくキリンだ。そう断言できる。この経験がなければ、私たちは「食」を支える一次産業の実態をこれほど知ることはなかっただろうし、キリンの存在意義を真正面から捉え直すこともなかっただろう。(2018年3月8日掲載)

巨大な揺れが大地を襲い、津波が町を飲み込んでいく。まるでフィクションのような現実が降りかかったあの日。自然の脅威を目の当たりにした僕らは、今までの価値観を地中の奥底から揺さぶられた。そして、日本中の人たちが大なり小なりこう考えたはずだ。「自分は今、どこに立っているのか」「自分にとって大切なものは、何だろうか」と。(2018年3月6日掲載)
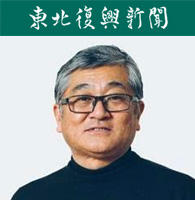
震災後私たちが目指してきたのは、被災した東北を単に震災前の元の状態に戻すのではなく、よりよい地域・社会を新たにつくり上げることだった。私が考える新しい社会とは、1人ひとりがその人らしく暮らせるための居場所があること。子どもも大人も、高齢者や障害者などの社会的弱者も、みんなが必要とされ、安心して暮らせる社会だ。(2018年2月28日掲載)
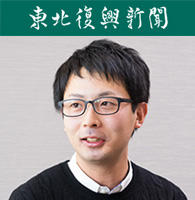
あの震災から7年近くが経った今、強く実感することは、僕らが活動する岩手県や東北を含めて、全国的に地域志向の人が増えたことだ。東京一極集中や大企業への就職など、これまでの社会の流れや風潮に漠然とした違和感や疑問、不安を感じ、都会から地方に移って起業したり、「地域おこし協力隊」として働いたり、学生が地方企業のインターンに参加したりと、地域との接続が強く、太くなってきている。(2018年2月25日掲載)
 岩手県で若者が主体的に活動するためのネット―ワークづくりをサポートするwiz。その中核事業のひとつである就業体験プログラム「IWATE実践型インターンシップ」は、地域が抱える社会課題を解決しようという想いを持ち奮起している企業・経営者と、学生のコーディネートを行っている。
岩手県で若者が主体的に活動するためのネット―ワークづくりをサポートするwiz。その中核事業のひとつである就業体験プログラム「IWATE実践型インターンシップ」は、地域が抱える社会課題を解決しようという想いを持ち奮起している企業・経営者と、学生のコーディネートを行っている。
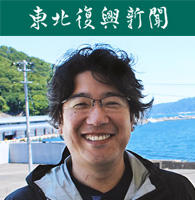
あれから7年近くが過ぎた今、釜石が「俺の町」ではなくなりつつあるかな、というのが正直な気持ちだ。震災から3年経ったあたりから「そうなったら嫌だな」という思いが、現実になりつつある不安を感じている。どこか「他人の町」になってしまっているのではないか。そんな危機感がある。(2018年2月18日掲載)
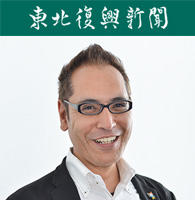
木々が生い茂る山奥に、薄い壁を隔てただけの簡素な仮設住宅。2013年4月、僕は丸の内のビジネスマンとして「復興支援」の任務を背負い、見ず知らずの町・気仙沼へ送り込まれた。大阪と東京しか知らず、地域活性なんて右も左もわからない僕にできることは、何だろうか。(2018年2月13日掲載)
 岩手県で若者が主体的に活動するためのネット―ワークづくりをサポートする「NPO法人wiz(ウィズ)」(以下、wiz)。就業体験プログラム「IWATE実践型インターンシップ」やクラウドファウンディング「いしわり」のほか、U・Iターン者の支援などの活動でアクションすることを岩手のスタンダードに。
岩手県で若者が主体的に活動するためのネット―ワークづくりをサポートする「NPO法人wiz(ウィズ)」(以下、wiz)。就業体験プログラム「IWATE実践型インターンシップ」やクラウドファウンディング「いしわり」のほか、U・Iターン者の支援などの活動でアクションすることを岩手のスタンダードに。