
平坦な土地に広がる農地が壊滅的な被害を受けた宮城沿岸最南端のまち、山元町。2015年、農業の再生を目指して100haという広大な農地に機械化・IT化を整備し、農業法人が設立された。しかし、思うように業績が上がらず、赤字が続く。そこで経営改革を託されたのが、JA全農みやぎ職員として再生計画の立案に携わった馬場仁さんだった。

平坦な土地に広がる農地が壊滅的な被害を受けた宮城沿岸最南端のまち、山元町。2015年、農業の再生を目指して100haという広大な農地に機械化・IT化を整備し、農業法人が設立された。しかし、思うように業績が上がらず、赤字が続く。そこで経営改革を託されたのが、JA全農みやぎ職員として再生計画の立案に携わった馬場仁さんだった。
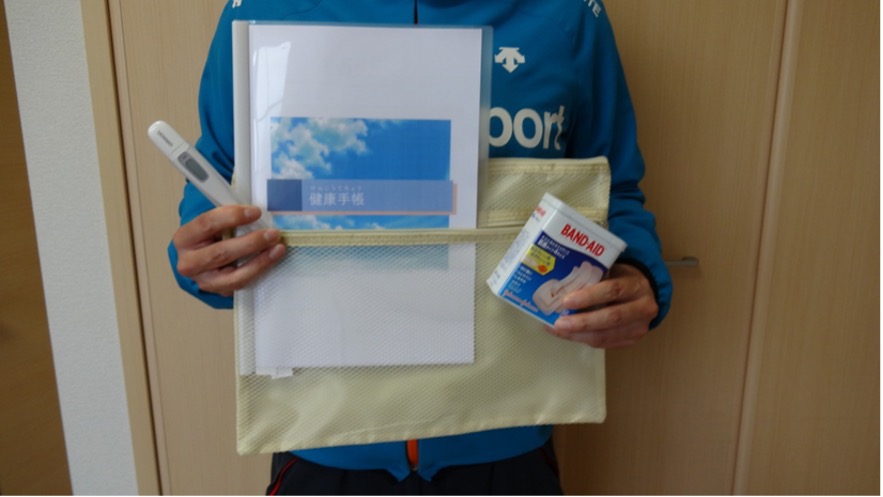
看護師として世界の貧困地域や開発途上国を旅しながら、格差や不平等への違和感を胸に抱き続けた澤田和美さん。福島第一原発事故が起き、不平等や不条理が自分の足元にもあった事実に愕然としたという。仕事を投げうって福島へ移り、専門性を活かして児童養護施設の子どもたちのための活動を始めた。「新しい東北」復興・創生の星顕彰の受賞にあたり、「自分で声を上げられない子どもに寄り添いたくて続けてきた活動。光を当てていただきありがたい」と話した。

福島第一原発事故により全村避難を余儀なくされた福島県葛尾村。住人が少しずつ戻ったとき、主幹産業だった農業・畜産業・林業はいずれも放射能汚染の風評被害にさらされた。「故郷を蘇らせたい」と地元出身の兄弟が立ち上がり、コチョウランの生産を始めた。作り手のリーダーとして抜擢されたのが、群馬県出身の丸山剛史さんだ。

東日本大震災が起きたのは大学卒業の目前。「俺が行くしかないと“勘違い使命感”が湧いて」。加藤拓馬さんは身一つで気仙沼市唐桑に入った。以来11年、目の前にある課題と向き合い、地域を巻き込んで仕事を生みだし、悩み迷いながら突き進んできた。「新しい東北」復興・創生の星顕彰の受賞にあたり「地域の皆さんが自分ごととして喜んでくれたことが一番うれしい」と話す。

誰の目にも留まらない古い民家を蘇らせ、シェアハウスにしてユニークな人材を呼び込み、石巻にイノベーションを起こしつづける巻組。もともとはボランティアとしてやってきた、現在代表を務める渡邊享子さんが移住して立ち上げた事業は、さまざまな人を巻き込み巻き込まれ、今もむくむくと夢を膨らませている。「新しい東北」復興・創生の星顕彰の受賞について、2021年に入社し広報業務を担う平塚杏奈さんは「ここまでの頑張りを認めていただきありがたい。今後は被災地外にも活動を広めたい」と話した。

大船渡市の賑わいの中心「キャッセン大船渡エリア」。アースカラーを基調とした商業施設や宿泊施設などが集積する同エリアの中央に位置する「商店街区」には地元の飲食店や商店が軒を連ね、まだ若い木々が広場を彩る。地元住民が普段の買い物に訪れ、週末にはイベント目当てに観光客も足を運ぶ。津波で被災した街の再生を目指し、「エリアマネジメント」の手法を用いて整備した。運営を担うのは官民連携によって誕生したまちづくり会社・キャッセン大船渡だ。

津波到達地点にコツコツと桜を植え続ける人たちがいる。目標は170キロの長さに1万7千本。この壮大な夢は「もっと助かったはずの命」を未来の人に後悔させるまいという切実な願いからスタートした。「新しい東北」復興・創生の星顕彰の受賞に際し岡本翔馬代表理事は、「大変ありがたく、活動が形になってきたことの証だと思う。寄付者やボランティアの皆さんと喜びを分かち合いたい」と話した。

地域のお母さんたちが趣味の延長で始めた読み聞かせグループ「おはなしころりん」。図書館で、学校で、公民館で、自分たちも楽しみながら絵本や紙芝居の世界を伝えてきた。ところが東日本大震災が日常を一変させた瞬間、彼女らの活動もガラリと色を変え深まった。“おばちゃん”ならではのコミュニケーション力としなやかさ、たくましさで、住人と地域全体を元気づける活動を息長く展開している。

福島第一原発事故により、双葉郡8町村の多くの住人は身一つで避難を余儀なくされた。いつ戻れるか、家はどうなっているのか、友人はどこにいるのか、誰もが切実に情報を求めた。平山勉さんは避難直後から情報を発信し、2035年「昔の寄り合いみたいに用がなくても集まろうや」と「双葉郡未来会議」を設立。町や村の境を超えた活動を続ける。「新しい東北」復興・創生の星顕彰受賞の知らせに「うれしいです。同時にもっと頑張らなきゃと気合が入りました」と表情を引き締めた。

地震や津波、土砂崩れ、洪水などの自然災害が起きたとき、空から撮った画像をリアルタイムで共有できればこれまでより格段に早く効率的に対応策が取れ、被害を少しでも食い止められるのではないか。そんな夢のプロジェクトを進めているのが、株式会社テラ・ラボだ。「新しい東北」復興・創生の星顕彰の受賞にあたり、代表の松浦孝英さんは「まさかと驚いた。ひたすら走り続けて孤独を感じることもあったが、やってきてよかったんだと思えました」と喜んだ。

結婚を機に華やかな都会暮らしに別れを告げ、震災後の気仙沼へやってきた藤村さやかさん。「よそ者目線」で捉えた社会課題に正面から立ち向かい、子育て中の女性が生き生きと働ける藍染め工房を設立した。女性らしい感性を表現した商品は話題を呼んだがそれに満足せず、原料となる植物の栽培にも挑戦。自分たちの足元からここにしかない「気仙沼ブルー」を生みだし、「地方における多様な働き方の実現」に向け、さらなる高みを目指して未来を見据える。