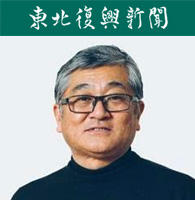
震災後私たちが目指してきたのは、被災した東北を単に震災前の元の状態に戻すのではなく、よりよい地域・社会を新たにつくり上げることだった。私が考える新しい社会とは、1人ひとりがその人らしく暮らせるための居場所があること。子どもも大人も、高齢者や障害者などの社会的弱者も、みんなが必要とされ、安心して暮らせる社会だ。(2018年2月28日掲載)
各メディアで掲載されている、東北の明日を切り拓く取組をご紹介します。
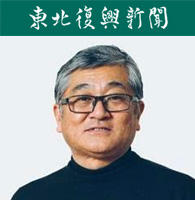
震災後私たちが目指してきたのは、被災した東北を単に震災前の元の状態に戻すのではなく、よりよい地域・社会を新たにつくり上げることだった。私が考える新しい社会とは、1人ひとりがその人らしく暮らせるための居場所があること。子どもも大人も、高齢者や障害者などの社会的弱者も、みんなが必要とされ、安心して暮らせる社会だ。(2018年2月28日掲載)
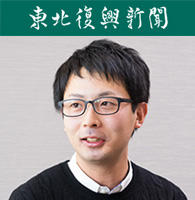
あの震災から7年近くが経った今、強く実感することは、僕らが活動する岩手県や東北を含めて、全国的に地域志向の人が増えたことだ。東京一極集中や大企業への就職など、これまでの社会の流れや風潮に漠然とした違和感や疑問、不安を感じ、都会から地方に移って起業したり、「地域おこし協力隊」として働いたり、学生が地方企業のインターンに参加したりと、地域との接続が強く、太くなってきている。(2018年2月25日掲載)
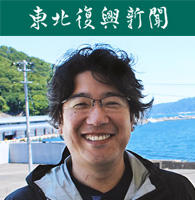
あれから7年近くが過ぎた今、釜石が「俺の町」ではなくなりつつあるかな、というのが正直な気持ちだ。震災から3年経ったあたりから「そうなったら嫌だな」という思いが、現実になりつつある不安を感じている。どこか「他人の町」になってしまっているのではないか。そんな危機感がある。(2018年2月18日掲載)
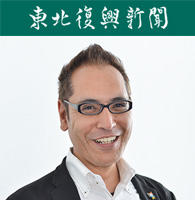
木々が生い茂る山奥に、薄い壁を隔てただけの簡素な仮設住宅。2013年4月、僕は丸の内のビジネスマンとして「復興支援」の任務を背負い、見ず知らずの町・気仙沼へ送り込まれた。大阪と東京しか知らず、地域活性なんて右も左もわからない僕にできることは、何だろうか。(2018年2月13日掲載)
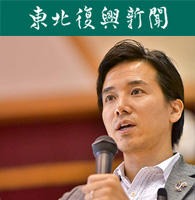
震災後の約7年間、歴史や社会の変化をこれほどダイナミックに肌で触れる感覚を味わうのは、初めてだ。2011年3月12日、福島第一原発1号機が爆発した映像を目にした瞬間、私の中で何かがはじけた。すぐにそのとき働いていたマッキンゼーを休職し、災害支援を行うNPOと契約して仙台へ向かった。(2018年2月7日掲載)
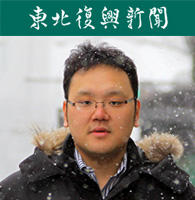
数多くの変革者やチャレンジャーが生まれた。それが、震災後の東北で起きたポジティブな変化だ。被災地には、従来の経済合理性ではないものに価値や生きがいを見出し、社会や地域のために活動する人が東北内外からたくさん押し寄せた。さらに、そうした挑戦者を支えたり、あるいは触発されて自ら起業するようなプレイヤーも生まれた。(2018年2月4日掲載)

ビールとワインの空瓶が部屋中に転がり、テーブルの上にはタバコの灰が散らばっている。あれは、震災後1年のとき、私たちが現地で自らの支援がニーズに即しているか、課題解決となっているかを検証するために家庭訪問をしていた。そこで目に飛び込んできた光景が、どうしても忘れられない。(2018年1月31日掲載)
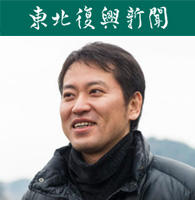
小学校には、保健係や図書係などの様々な「係」がある。社会を「学校の教室」という小さな単位に例えた場合、あなたは「何係」だろうか?震災後、多くの個人や組織に芽生えたのは、そうした社会におけるそれぞれの「役割の再定義」だったのではないか。(2018年1月29日掲載)
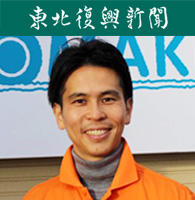
社会の「振り子」が戻り始めた。震災後の変化を一言で言うならこういうことだろうか。これまでの価値観が大きく揺さぶられ、生きる意味を見つめ直す種火のようなものが、個々の心の中で燃え出した。それは、行き過ぎた資本主義に対する「本当にこのままでいいのか?」という警告と揺り戻しだったのではないか。(2018年1月24日掲載)

僕は震災前、石巻という町に不満とあきらめを抱いていた。徐々に広がっていく商店街のシャッター通り、閉鎖的な人間関係、古いしがらみ、力をもつ一部の人たちだけで決める物事の進め方、そんな地域に対して若者が抱く将来への閉塞感…。震災は確かに大きなダメージだったけど、単に震災前の状態に戻すだけでは不十分だった。(2018年1月19日掲載)