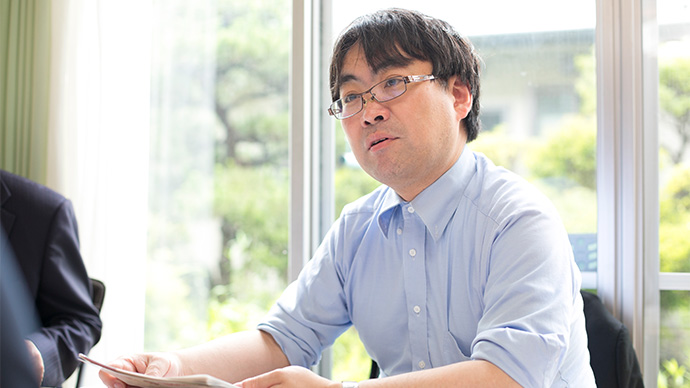
1999年、フリースクールからその活動をスタートさせた、特定非営利活動法人ビーンズふくしまでは、震災および原発事故による大きな混乱が続く中、被災した子どもの居場所づくりや学習支援、親子の心のケア、県外避難者親子の支援などに注力。行政・民間・市民の連携によって、地域で子どもを支える新たなコミュニティ再生を目指している。
「人に寄り添う」ソフト面の支援がより重要になる
被災した子どもに寄り添うため、ビーンズふくしまがトヨタ財団、パナソニック教育財団等の協力を得て、2011年9月にスタートさせた「うつくしまふくしま子ども未来応援プロジェクト」。その活動内容は、子どもの居場所づくりや学習支援、親子の心のケアなどが中心となったが、誰もが経験したことのない状況下での取り組みゆえ、すべてが手探りの連続だった。
プロジェクトリーダーを務めた常務理事の中鉢博之氏は、事前調査したアセスメント・データをもとに、ビーンズふくしまと福島大学の学生のグループが連携して、被災した子どもが多いと思われる10数か所の仮設住宅を巡回した。
「原発事故の影響で、支援団体が入っている地域と入れない地域に格差があり、支援者やコンスタントに活動できるボランティアが不足し、交通手段の確保が難しかった」(中鉢氏)。
専門性の高いボランティアの不足、みなし仮設(借上住宅)への支援が届けられない状況、資金・労力面で継続的に支援体制をとれる団体・グループの少なさなど、課題は山積していた。それでも、地域住民や自治会の協力、週末や休日を利用した社会人ボランティアの参加などがあって、少しずつ状況が好転していったという。資金的な協力が、的確なコーディネートを経て地域の自発的な行動を促していったのだ。
民間・市民主導で進んだ本プロジェクトだが、その後、活動内容の拡大に伴ない被災者支援交付金等を積極的に活用。また、避難者を多く抱える浪江町や富岡町の教育委員会、川内村等の自治会、学校等の協力が得られ、ふるさととの絆が途切れなかったこともプロジェクト推進の後押しとなった。
「行政との関係でいえば、実務作業は地元NPOに委託するなど、早めに役割を分担した方が、短期間に結果を出しやすい。逆に、私たちが県外避難者の支援活動を行う際には、県や復興庁の協力が強みになる」と、中鉢氏は官民連携・協働の意義を強調。当初、厚生労働省からの要請で設立されて、被災3県に現地窓口を置いた東日本大震災中央子ども支援センター(福島県の窓口をビーンズふくしまが担当、2014年より「ふくしま子ども支援センター」)は、福島県との官民協働で福島の子どもの心のケアを進めてきた。
震災から8年が経過し、目に見えて復興が進むものがある一方、子育てや心のケアを巡る後発性の問題なども顕在化している。息長く見守る支援が必要になることから、ビーンズふくしまでは、福島市に“地域の居場所”となる「みんなの家@ふくしま」と「みんなの家セカンド」を開設した。
当時サポートした子どもたちは成人を迎え、社会との接点を広げようとしている。一方、移住してくる子育て世代には、未だ風評や不透明な情報に振り回され、不安とストレスを抱えるケースもあるという。
「これから求められる支援はハードよりもソフトの部分。私たちは地域の人々に寄り添いながら一緒に課題に取り組み、復興の道筋を示すお手伝いをしていきます」(中鉢氏)。
ビーンズふくしまの取り組みは、持続的な地域づくりをしていく中、今後さらに重要なものになる。
特定非営利活動法人ビーンズふくしま(福島県福島市)
http://www.beans-fukushima.or.jp/
