Fw:東北Fan Meeting 2022 東北デジタル創生塾Vol.8 草の根で目指すデジタルデバイド解消の方策とは ~陸前高田市の事例から地域活動としての広がりを考える イベントレポート

地域でデジタル活用を進めるにあたり、その地域で暮らす人々が、デジタル機器やサービスをどのくらい使いこなせるか。この問題が、地域のとって大きな壁になっているケースも少なくありません。デジタルを使いこなすスキルが人によって異なり、格差を生み出している状態が、「デジタルデバイド」という言葉で語れる場面が多いのも事実です。
その対策として、高齢者向けのスマホ教室や、若年層向けの学校での支援活動など、民間と行政が力を合わせて場を起こし、活動を起こしているケースも増えていますが、民間側ではどのような担い手が、何を目指して活動を続けているのでしょうか。
今回の東北デジタル創生塾では、地域の困りごとの解決に向けて岩手県陸前高田市で活動を展開する一般社団法人トナリノから、東北暮らし発見塾でも登壇いただいた山本健太さんをお迎えし、東北でのデジタルデバイド解消の動きとして必要なことは何かを、様々な視点で語り合いました。
また、他地域での事例紹介として、兵庫県たつの市でシニア向けに「地域デジタルマイスター養成講座」の立ち上げを進めている特定非営利活動法人いねいぶるの宮崎宏興理事長をお招きし、地域を超えて工夫を活かし合う仕掛けづくりについても議論を行いました。
さらに、総務省
地域情報化アドバイザーとして太田垣 恭子氏も交え、シビックテックと一緒に起こせるアクションや、デジタルを苦手とする方々へのケアを通じて、DXを進める側にとって活かすべきニーズがあるのかなども含め、幅広に議論を行いました。
インプットトーク
山本 健太 氏(一般社団法人トナリノ)
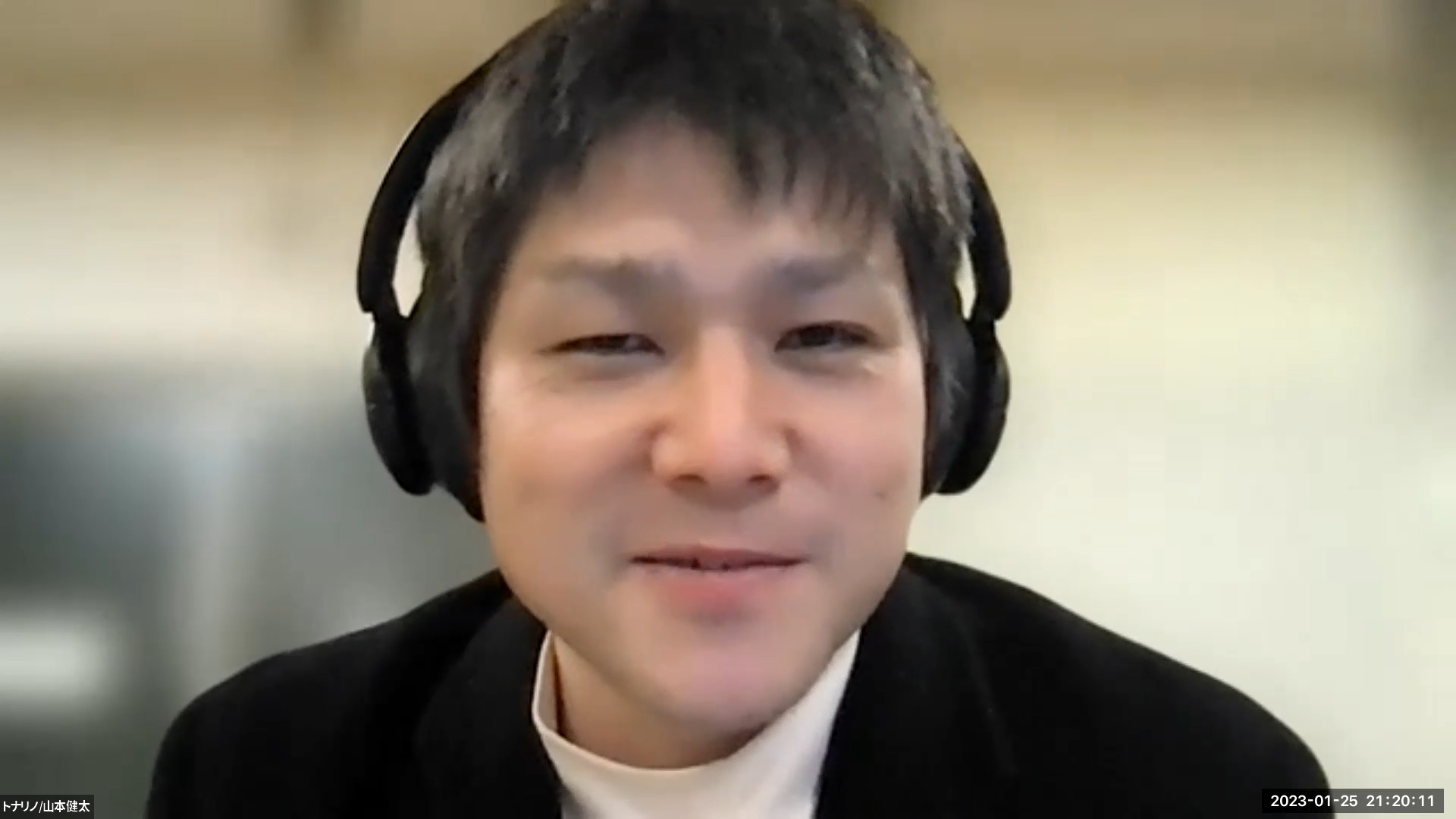
山本さんは、岩手県南部と沿岸地域を中心に、教育情報化コーディネータ認定委員会認定ICT支援員、デジタル大臣認定デジタル推進委員として、「スマートフォン教室」「デジタル活用支援員育成講座」「学校ICT支援」などを通し、「住民がデジタルを教わる機会を増やすこと」と「教える人材を増やすこと」を推進する活動を行っています。
日々の活動の中で山本さんは、教えてくれる人がいないから孤立して、デジタルを触れずに時間が過ぎてしまった住民が多いと感じているそうです。
山本さんは最後に「デジタル化についていけない人達の窓口となり、誰一人取り残されない状態を目指しています。私たちは、人の少ない地域で困りごとを聞きながら、それを解決していく状態・仕組みをつくることを大切にしていて、デジタルはそのための手段の一つだと考えています」とコメントしてくださいました。
宮崎 宏興 氏(特定非営利活動法人いねいぶる 理事長)
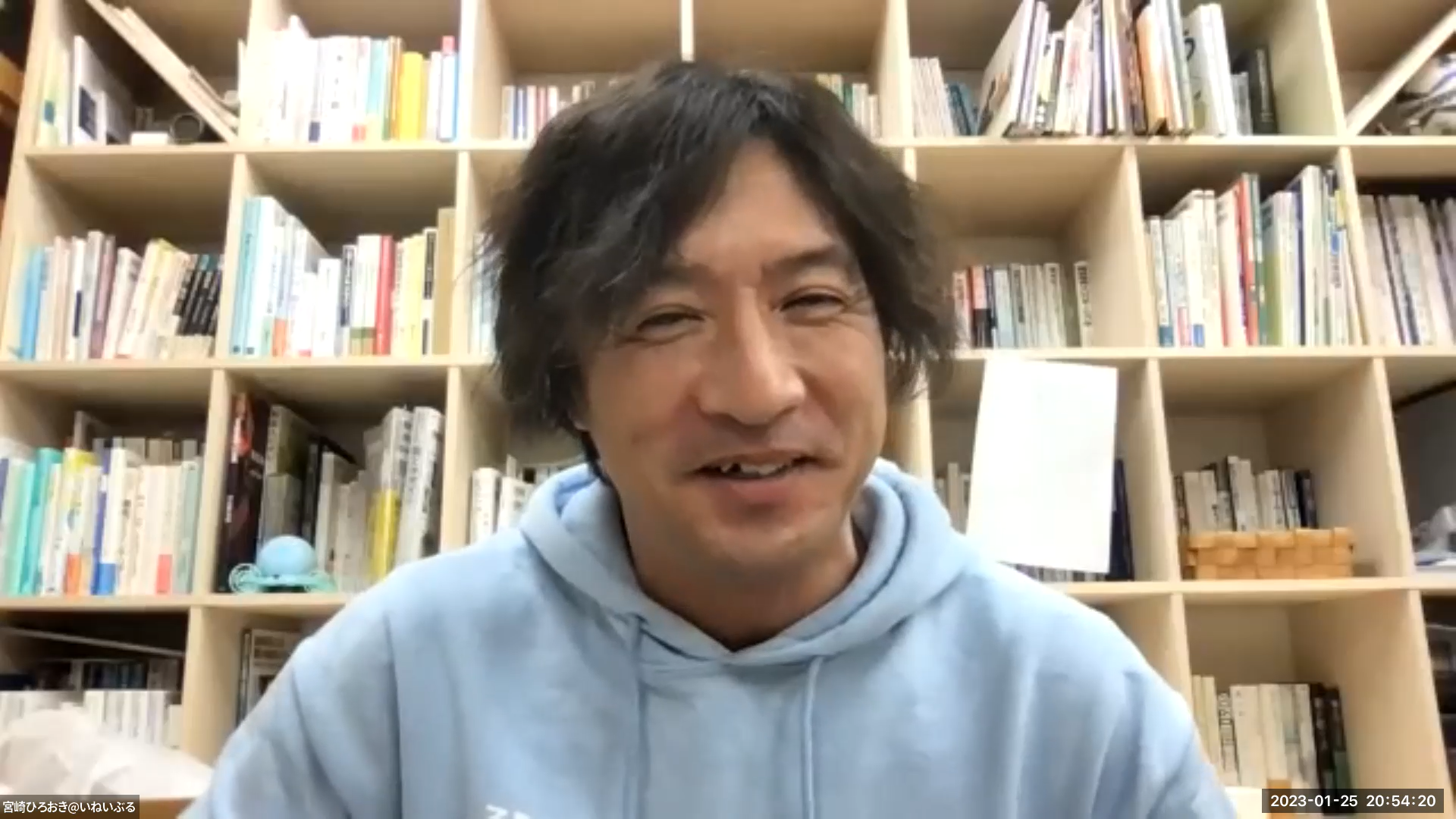
宮崎さんは、作業療法士や障がい者の就労・雇用支援の仕事をしながら、福祉制度を用いて人の暮らしで起こる問題を解決する「いねいぶる」人の暮らしを中心とした興味関心から広がる市民活動「T-SIPたつのソーシャルインクルージョンプロジェクト」などの団体で活動を行っています。
宮崎さんは、「老いた人にデジタルは難しいと言われるが、その『老い』は誰が決めているのだろう」と疑問に思っていた、とのことでした。高齢者の認知能力研究によると、加齢により記憶力は低下するものの、語彙や解決力は70代まで伸びると言われているそうです。宮崎さんは、「高齢者にデジタルはできない」と決めてかかる社会が問題なのではないか、と指摘されました。
また、高齢者との対話分析から、デジタル化のニーズは「困り感」よりもデジタルに触れることで知る「楽しさ」「生活の広がり」の方が大きいこと、デジタルに苦手意識がある人も、誰かに誘われれば受け入れる、という潜在的ニーズがあることがわかったそうです。
活動の一環として、ハンディカムでの撮影をミッションに、ご近所のおじいさんが数珠繋ぎを行う「じじつなぎ」新たな対話の場づくりとしての「ご近所デジタルマイスター養成講座」が紹介されました。
宮崎さんは、デジタルを使えない人は、老いの認識の問題なのか、孤立やコミュニティの問題なのか、無意識な不自由さなのか、何がバリアと定義するかでデジタルデバイドの対策は変わると思います、と示唆されました。
太田垣 恭子 氏(地域情報化アドバイザー/デジタル庁 オープンデータ伝道師/ANNAI Inc. 代表取締役副社長/Code for Kyoto 代表/Civictech.tv)
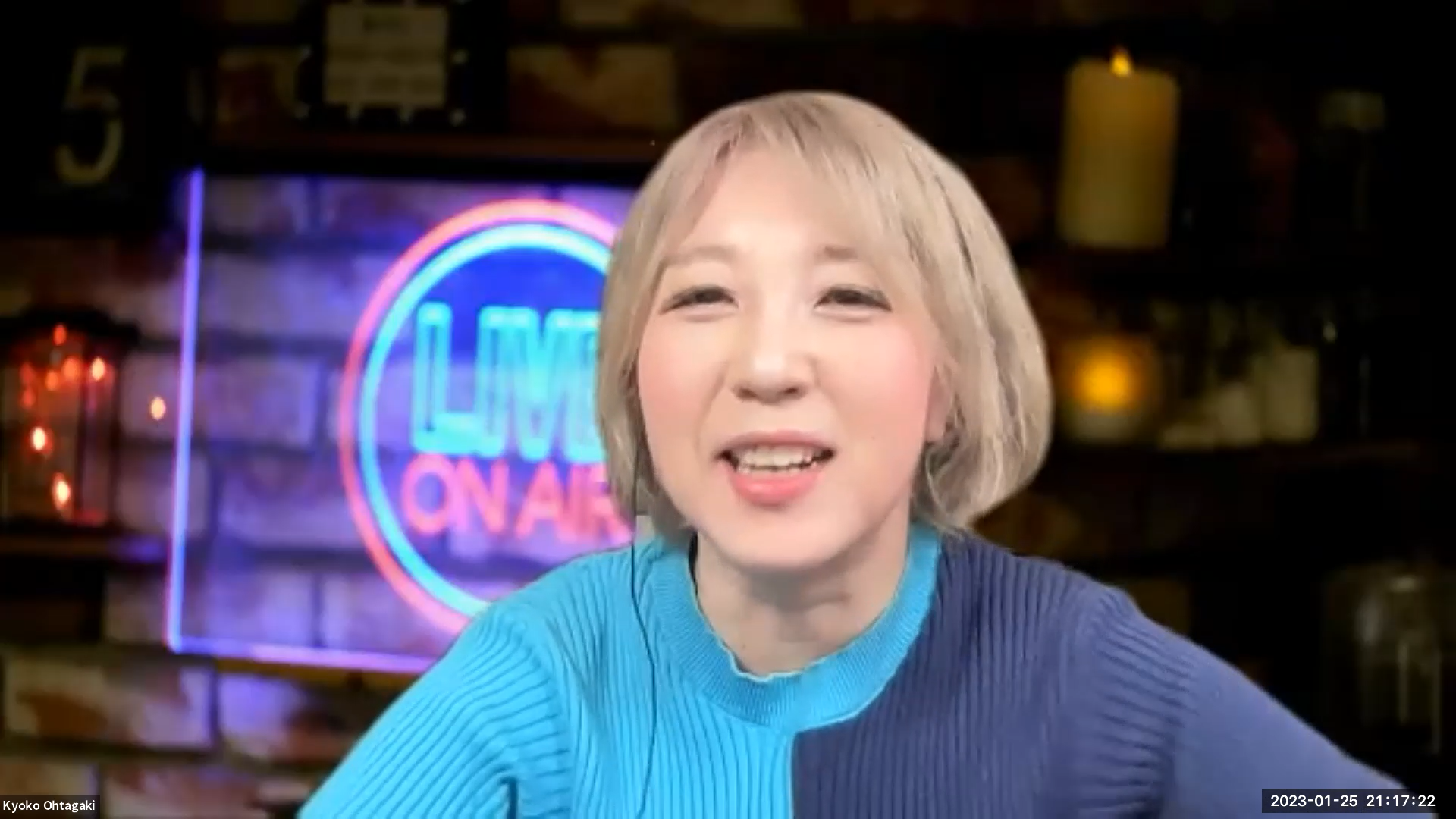
太田垣さんは行政・市民がつながるコミュニティの運営、Facebookライブ「Cテレ」YouTube対談番組「スナック恭子」の運営など、公私ともにDXやデジタルをもっと身近にしてもらえるように様々な活動に取り組んでいます。
太田垣さんは、コロナ禍で外との接点が減り、自分は社会や地域とつながっていると思っていたが実際は違っていたのではないか、と感じ地域コミュニティに属していない自分が地域課題を解決する活動をしていることに疑問を抱いたそうです。
自分のポリシーを再考して(1)シビックテックにこだわらず、いまあるサービス・仕組みをよくしたい。(2)地域や社会をよくしようって頑張る人たちを応援していきたい。(3)ネガティブをポジティブで上書きしていきたい。との思いで活動をしている、とのことでした。
太田垣さんは最後に、「シビックテックが地域活動とは違うものとしてとらえられることもありますが、自分の周りにあることを良くしたい、今よりもっとステキな世の中にしていきたいと思えばできることがあるのではないか、私はそれがシビックテックの活動になると思っています」とコメントしてくださいました。
登壇者・参加者のみなさんとのオンラインセッション

次に、ファシリテーターの原亮(エイチタス株式会社)を交え、登壇者・参加者とのトークセッションが行われました。
「地方や人との接点が少ない人が、行政や地域の最新情報をどのように取得できるか」
「デジタルを使った課題解決を民間・行政から推進していく必要性」
「デジタルに拒否反応を示す人を取り残さないために何をするべきか」
などのテーマが扱われ、セッションを通して、自分でできるようになる喜び、暮らしの豊かさ、楽しさなどを体現していくための手段の一つがデジタルであり、地域のコミュニティ活動と掛け合わせると最初のきっかけになること、一方的に教わるだけではなく教えることもできる関係性を作ることの大切さが示唆されました。
参加者からは、「デジタルだけに突出せず地域コミュニティとの日常化がデジタル化を推進させるのだと思いました」「一方的ではない伝え方を考えるきっかけになりました」「親のマイナンバー手続きを優しく教えたいと思いました」などの感想もあり、盛況のうちにセッション終了となりました。
参考リンク
- • 山本 健太 氏(一般社団法人トナリノ)の資料はこちら
- • 宮崎 宏興 氏(特定非営利活動法人いねいぶる 理事長)の資料はこちら
- • ANNAI Inc
- • Code for Kyoto
会議概要
- 日時:2023年1月25日(水) 19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:45名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
