
「原子力被災12市町村」の南相馬市生まれの本田紀生氏が、本業である広告業に携わる有志たちと2010年に福島市で設立。現在は川内村を拠点に、同村の地域活性化プロジェクト「かわうち@WORK」や、浜通りを中心に被災した各所を巡る「福島伝承スタディツアー」などを行っている。また、広告業で得たコネクションを活かし、台湾との交流事業を中心に、海外に向けた「福島」の発信にも積極的に取り組んでいる。
広告業を出発点に
――最初に、御法人のご紹介をお願いいたします。
当法人は2010年10月25日、東日本大震災のおよそ4ヶ月半前に設立いたしました。元々私は広告の仕事が本業で、もう40数年やっておりますが、広告業界の仲間たちと福島市の中心市街地を活性化するという目的でNPOを立ち上げました。それから4ヶ月半後に東日本大震災が発生したのですが、私は福島県のいわゆる「原子力被災12市町村」の一つである南相馬市、厳密に言えばかつての原町市というところの生まれです。加えて、小学校から移った福島市、父親の生まれ故郷である田村市、母親の出身地であるいわき市、さらには私が高校から大学にかけて過ごした宮城県仙台市と、私や両親にゆかりのあるところが全て、今回の東日本大震災の被災地になりました。当時は広告業に携わって30年ちょっと経っており、様々な広告をベースとした地域活性化やブランディングの仕事をずっとしていましたので、私の経験を踏まえて被災地の復興について何かお手伝いができないかということで法人を設立し、現在に至ります。
――広告業界で働こうと思われたきっかけは何ですか?
最初は新聞記者かテレビ局の報道関係に進みたいと思っていたのですが、私の世代だとそれらはかなり狭き門で、採用枠も1社につき1~2名程度でした。一応、色々受けてはみましたが、残念ながら上手くいかなかったんですね。そうしている中で広告代理店をいくつか受けたところ、とある代理店が採用してくれて、やはり自分の希望としては「情報を多くの方々にお伝えするような仕事をしたい」とずっと思っていましたので、それをきっかけにこの業界に入り、以来ずっと広告業に携わっています。
――震災以前からあった福島県の課題としては、どのようなことが挙げられますか?
一口に「福島」と言っても、地域によってかなり違いがあるんですよ。今回の被災は浜通りが中心ですが、他にも県内には私が住んでいる福島市や中通り、さらには会津地方などもあり、それらを一緒くたにして「福島とは何ぞや?」ということはなかなか言えない大きな県なんですね。とはいえ、やはり地方都市ですので、他の地方都市における色々な課題と共通している部分は多いと思います。例えば、駅前の通りが衰退してシャッター通りになってしまっているとか、県庁所在地にしても地方都市は特に高齢化が進んでるとか、です。これらの問題は福島県に限らず日本の各地で起こっており、私も全国にいる地方の地域活性化に取り組む仲間と繋がって色々な活動を一緒にやっていますが、今申し上げたような話を頻繁に耳にします。その上で福島に関して言えば、やはり13年前の東日本大震災で、今挙げた問題がより深刻化したというのは間違いないと思います。

「福島」のグラデーション
――地域の活性化においては、震災後はどういった取り組みから始められたのでしょうか?
震災後については、やはり地域の方々から色々とお話を伺い、その上で地域の行政との関係を繋ぐことはもちろん、私どもの団体の信用を築いていく必要があるので、まずはそこからスタートいたしました。先程も申し上げたように、私は元々南相馬市の生まれですが、被災地の支援については福島市から赴いていましたので、「『よそ者が来た』と思われるかもしれない」という思いは少なからずありました。県外からの支援もそうですが、同じ福島県内であってもやはり地域の違いが大きいので、地域住民の方々からしっかりと情報やニーズをお聞きするにあたっては、「信頼関係を築く」ということを念頭に置いて活動に取り組んでまいりました。なので、震災後の最初の2~3年は、住民の方々との信頼関係を築くのに注力しました。
――「一口に『福島』と言っても、地域によってかなり違いがある」と先程仰っていましたが、浜通りの中でも地域によって細かな違いがあるのでしょうか?
仰る通りで、これは住民の方々のお話を伺って分かったことですが、浜通りでも地域によって住民の方の考え方が異なるということが結構ありました。私どもが少しずつ色んな方々からお話を伺って、現状抱えている問題や要望などをお聞きすると、やっぱり地域でグラデーションがあるんですね。「なぜ違いがあるのだろう?」とずっと考えていたのですが、考えていくうちに分かったことがあって、それは何かというと、旧藩の区分けの問題です。かつての浜通りは「夜ノ森」というところを境に、南側は磐城平藩、北側は相馬中村藩の藩領でした。そのため、そうした藩の考え方が脈々と受け継がれている部分が現在もあり、それが住民の考え方の違いにも表れているのではないかと考えられます。このことに気付いたことで、地域ごとの考え方の違いについても合点がいき、それからはそれに基づいた関係性作りを意識して取り組んでまいりました。
――今のお話は、県外にいるとなかなかイメージするのが難しいと思います。
実際そうだと思います。例えば先程申し上げた「原子力被災12市町村」という呼称についても、「原発事故で避難指示の対象になった地域」という意味ではその通りではあるのですが、一方で12市町村一つ一つで被害や復興の状況はもちろん、地域住民の方々の考え方も全く異なりますし、一言で「震災のとき、福島はどのような状況だったか?」、あるいは「今の福島はどれぐらい復興したのか?」と問われても、一概には答えられない現状があります。
「悔しさ」から始めた復興事業
――御法人では震災後、どのようなことを目標として活動に取り組んでいこうとしたのでしょうか?
大きなコンセプトとしては、やはり「復興」ですね。具体的には「震災前に戻るのではなくて、それ以上のまちづくりをする」ということ、それこそが自分の仕事だと考えました。どういうことかと申しますと、今年(2024年)は1月に能登半島、4月には台湾(花蓮地震)でそれぞれ大きな地震がありましたが、災害が発生すると、最初は物資や食料などの不足が問題となってきます。それがある程度解消されると、今度は生活に必要なインフラの復旧・確保が行われます。私の言う「復興」というのはそれらの後の話で、地域の方々のお話を傾聴し、そこから課題を抽出してその解決方法について考えていき、具体的な内容について検討するというのが、私ども法人の仕事だと思っています。その際、復興事業というのは文字通り「事業」ですから、当然ですが予算を国や県から引っ張ってきて、皆様のお力をお借りしながら進めていかなければならない。そうである以上、単に13年前の状態に戻すのではなく、事業として行うからには福島を震災前以上の場所にしていきたい。それが私どもの信念ですね。
――このインタビュー前に実施させていただいた事前アンケートでも「復興」や「新しい」ということがかなり強調されていましたが、これにはどのような理由があるのでしょうか?
一言で言えば、福島県民である私自身の悔しさが根底にあります。というのも、福島県には全国トップというものはあまり多くありませんが、それでも首都圏を中心に日本の食を長らく支えてきたし、東京電力にしても関東地方の電気を支えてきました。また、福島県には優れた農産物が沢山ありますし、お酒も全国新酒鑑評会で、2012年度から2021年度にかけて9回連続(※2019年度はコロナ禍の影響で選定見送り)で日本一になっています。だけど、震災でそうした物を作る方々が被災し、加えて福島県では岩手県や宮城県とは異なり原発災害が発生しました。そのため、実際には影響がなくても「放射能で汚染されている」という風評被害も多発しました。そうした状況を見て、私は「大好きな福島県がゼロに近い状態になってしまった」と思ったんですね。もちろん、福島県内でも地域によって状況は異なりますが、とはいえ、それがやっぱり悔しくて、だからこそ「元に戻すのではなくて、それ以上のまちづくりをしていかないと駄目だな」と考えた次第です。
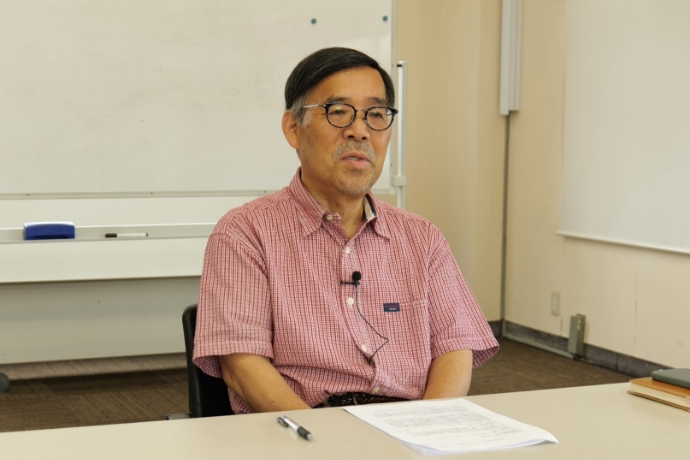
現在の活動内容
――今のお話を踏まえた上で、現在の活動内容についてお聞かせください。
現在取り組んでいることは主に三つありまして、それぞれ順番にご説明しますね。まず一つ目は、先程も申し上げた川内村の農業支援を中心とした「かわうち@WORK」で、現在では農業支援の他にも、他の都道府県からの移住・定住者の支援事業や特産品のPR事業などを中心に、川内村の地域活性化に関するプロジェクトの構築についての支援やコンサルティング業務を全般的に行っています。
次に、二つ目が「福島伝承スタディツアー」というもので、これは震災の記憶の伝承を目的に、浜通りを中心に被災した各所を巡る2泊3日のツアーです。ツアーが現在の名称になったのは2021年からですが、そのベースが実はありまして、アメリカの社会変革ファシリテーターであるボブ・スティルガーさんという、地域や組織の活性化の方法としての「ダイアログ」、つまりは対話のための場作りに長年取り組んでおられる方がいます。ボブさんとは彼が2012年に南相馬市に来てくださった際にご縁ができたのですが、それからしばらくしたある日、ボブさんのご紹介でアメリカから彼のご家族やご友人が20人くらい来てくださったんですね。「今の福島をぜひ見てみたい」ということだったので私がアテンドしたのですが、これを事業化したらどうだろうかと思い、2015年から「福島ラーニングジャーニー」を始め、これが現在の「福島伝承スタディツアー」の大元になります。ただ、コロナ禍の影響で活動が一旦途絶えてしまって、加えて震災から10年という月日が経過し、次第に振り返る機会も減っていったように感じました。だから2021年に再開した際に、「福島での災害における後悔や反省を教訓として伝え未来に残していくことが大切だ」という考えの下、現在の名称に変更いたしました。ツアー自体は大熊町との連携を昨年からスタートし、今年度は毎月やっていますので、このインタビューを読んだ方も、機会があればぜひご参加ください。
そして、最後の三つ目が「台湾との交流事業」です。先程も申し上げたように台湾とのご縁ができて20年以上経ちますが、事業自体のきっかけとしては、経済産業省の「地域の伝統・魅力等発信支援事業」の公募になります。私どもの団体では「福島の復興・魅力発信を通した台湾国内での福島を応援していただく台湾市民コミュニティ形成事業」と題して、日本に住んでおられる台湾人の若者による福島県取材ツアーや、台湾での福島の魅力発信イベントの主催などに取り組んでまいりました。なぜ台湾との連携を打ち出したのかと言いますと、もちろん私個人の台湾とのご縁もありますが、それとは別に福島、特に浜通りの復興について、「日本人だけでは難しいかもしれない」という風な気がしていたからです。原発事故は世界的にも注目されましたし、「今の時代は海外からも応援してもらえるような仕組みを作らなければならない」と思い、福島を海外にも積極的に発信していこうと考えたわけです。加えて、個人的には「浜通りを国際化したい」という思いがありまして、それもこの事業に取り組んでいる理由ですね。浜通りは現在、多くの国々から注目されていて、色々な事業が進んできていますので、様々な意味で沢山のチャンスがある地域だと私は思っています。だからこそ、そこに日本人だけでなく、全世界から優れた人材が来てくれるような仕掛けをしたい。そういう思いから、以前からご縁のある台湾や東京在住の台湾華僑の方々と一緒に色々試行錯誤しながら、この事業をスタートしました。
現在の課題
――震災から10年以上が経過し、御法人の活動においても様々な変化があったのではないかと思われますが、近年の課題としては、どのようなことが挙げられますか?
大きく二つの課題があると思っていて、一つは高齢化、そしてもう一つは「原子力被災12市町村」間における復興の度合いの違いです。12市町村で復興の度合いは一律ではありませんし、地域ごとに課題も異なります。震災から10年以上経過したこともあって、最近ではその違いが顕著になってきました。
――そうした課題の解決策の一つに他の地域からの移住・定住の促進があると思われますが、このことについて何か考えておられることはありますか?
これは私がずっと思っていることですが、完全な移住・定住は結構ハードルが高いと思うんですね。最終的に移り住んで定住してくださるためには、例えば元々住んでおられる住民の方々との交流の問題の他にも、仕事や住居など様々な課題があります。だから私どもが最近取り組んでいるのが、いわゆる「多拠点活動」の促進です。例えば、東京や大阪などを拠点に活動しておられる方に、福島にも拠点を作っていただく。そして、月の1/3や半分でいいから福島で活動する期間を設けていただければ、福島に通って事業が展開されるので、それに伴って交流の機会も増えていきます。実際、今は複数の拠点を移動しながら仕事をする人が少なくありませんから、多拠点活動を考えておられる方に福島を拠点の一つにいただければ、将来的には先程申し上げた課題の解決にも繋がっていくのではないかと考えています。
――他方で雇用創出については、今後どういった取り組みをしていこうとお考えでしょうか?
何よりもまず、今後に繋がる人材の育成が必要ですし、そのための仕組み作りをしていこうと考えています。地域活性化や雇用に関する法制度が明確に決まっている以上、制度のあり方そのものを変えることはやはり難しいです。また、特に当法人の場合、私を含めた現在中心的に動いているメンバーは私と同年代の人間ですので、我々が今後活動できるのは長くて10年程度かな、と。なので、今後10年の間に、次の世代にちゃんと引き継いでもらえるような、我々の活動を10年後から先にもきちんと後を引き継いでくれる人材の育成とその仕組みを、「仕事」としてしっかり作っていきたいです。そうしないと、活動しても何の収入もない状態では継続が難しいですから。

「復興」とは何か
――地域における雇用創出については、東京のような大都市に本社を構える企業が事業所や営業所を持ってきて、それで雇用を生み出すという事例が地方ではよく見られます。
それ自体も解決の糸口の一つにはなると思いますし、それ自体を否定するつもりはありません。ただ、一方で思うところもあって……例えば、最近はどこの都市に行っても、駅前の風景が同じように私には見えます。駅前にはコンビニやファストフード店があって、消費者金融やパチンコ屋があって……といった具合に、どこの都市も均一的、言い換えればその地域の「顔」が見えないまちづくりがとても多いような気がします。長らく地域の活性化に取り組んできた身としては、地域それぞれに異なる良さがあると思っていますし、それをきちんと考えた上での地域を盛り上げていかなくてはと考えています。雇用についても同様で、大手企業が来たはいいけれど、地域の良さを活かした仕事を新たに作るところまでは行っていないというケースが結構あります。そういった状況をやっぱり脱却していかなければいけないと私は感じていますし、地域にお金を落としていく復興活動をしていくべきだと思います。
――本田さんが「復興」について現在考えておられることについて、率直なご意見をお聞かせください。
震災から10年以上が経過し、今後は復興予算も削減されていくと思いますが、こういう予算についてはいずれなくなるべきだと個人的には考えています。予算は未来永劫あるものではないですし、お金がないから復興できないというのも変な話ですよね。なので、お金がなくても人が生活していけるような基盤作りがこれからは必要になっていくでしょうし、そうした中でできることを色々探りながら、今後も地方の再生、地域の課題解決に取り組んでいきたいと思います。少なくとも、これからますます課題が増えていく、あるいは顕在化していく以上、そういった事業はなくなりはしないと思っています。特に福島の場合、原発の廃炉の問題があって、その解決の糸口はまだまだ見えてきていません。巷では「廃炉まで30~40年かかる」とよく言われていますが、もしかすると100年以上かかるかもしれない。そうである以上、福島の再生事業というのはあと1世紀は続けないといけないし、そのための人材や事業を継続していくための仕組みを、自分が元気なうちに作っていかなければならない。少なくとも廃炉の問題が解決しない限り、福島の「復興」は完成しないと私は思います。
――最後に、御法人の今後の抱負についてお聞かせください。
幸いなことにベースの事業はいくつか見えてきているので、まずはそれらの継続と、場合によっては他の団体と連携しつつ、基本的には国の内外を問わず沢山の方々に福島県へ実際に来ていただいて、今後も福島の記憶や文化を後世に伝えるための事業を、現在行っているもの以外のバリエーションも検討しつつやっていければと思います。あと、当法人では今日もお話ししたように台湾との交流に力を入れておりますが、最近は「台湾と交流を持ちたい」、「台湾関連のフェスをやりたい」など色々な要望が全国からいただいていますので、台湾はもちろんのこと、アジア圏の国や地域と福島県がコラボレーションできるような流れを作っていき、情報の発信やイベントのコーディネートをしていければなと考えています。
