Cheer Up! ProjectVol.7人口ゼロになった町で持続可能な生活をつくるには~南相馬市小高区の私設公民館「アオスバシ」の挑戦イベントレポート

福島県南相馬市小高区は、東日本大震災での原発事故の被害により、一度、人がいなくなってしまった地域です。2016年7月に避難指示が解除され(帰還困難区域除く)、地域の人々の手により新たな日常をつくる営みが続いています。しかし、震災前に比べると、人口は3分の1程度までの回復に留まっています。
10年前に復興活動をきっかけに南相馬市へ移住をしたITエンジニアの森山貴士さんは、人口が激減した小高区で、地元へ戻ってきた人々や集団移転の高齢者たちが、持続可能でよい暮らしを送れるための営みとしてキッチンカーやカフェを手がけたのち、2022年には、空き店舗となっていた寿司店を改装し、コワーキングスペースと、パン屋、カフェを併設する「アオスバシ」を小高区に開設しました。
ビジネスとしての採算が難しい取組であっても、地域の人たちの生活をよくしていくためにできることは何か。アオスバシでは、店舗の品ぞろえやイベント開催といった工夫のほか、スタッフが自分たちで周辺の住宅を訪問して顔をつなぎ、地域の人たちが安心して足を運べる場づくりを手がけています。森山さんが示すのは、アオスバシが商いも営む“私設公民館”として、小高区に暮らす人たちの幸せを創る装置となっていくこと。この試みは、どのような意義を持っているのでしょうか。
今回のFw:東北Fan
Meetingでは、森山さんがアオスバシで地域の人々と作る日常や、その先に見えてくるものについて、お話しをしていきます。もうひとりのゲストとして、岐阜県大垣市でシェアキッチンを展開しながら、地域の人々の“共食”の場を作り上げている株式会社Coneruの平塚弥生さんをお招きし、地域の人たちが営みの場を共有することの意味を一緒に考えました。
挑戦者プレゼン
森山 貴士 氏(一般社団法人オムスビ 代表理事/公民館プロデューサー)
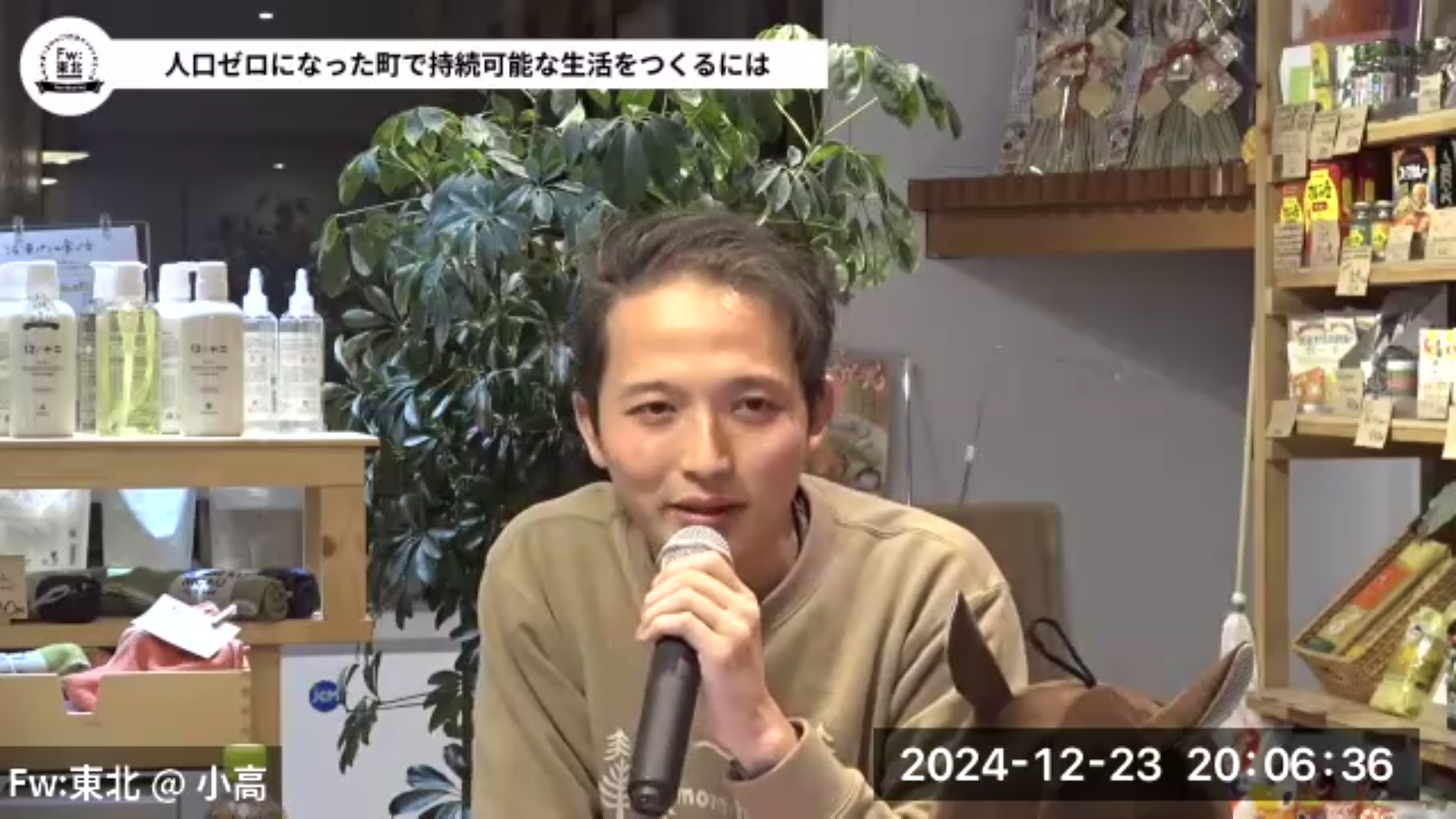
私設公民館アオスバシは、スペシャルティーコーヒーショップや「焼かないパン屋(冷凍パン専門店)」、オーガニック食品やこだわりの調味料などを取り揃えた食品のセレクトショップ、シェアキッチンといった食関連やワークショップ、コワーキングスペースなどを通して、震災後、地域の人々が豊かに暮らせる場を提供しています。
森山さんは、「アオスバシの利益が若干マイナスなので、元々の特技を活かしてウェブサイト作成なども行っています。市の子育て応援サイト・空き家バンクサイトの作成等を通して地域の情報発信を行い、地域の中での情報の流れを促進しています。
自分たちの活動は、一見バラバラに見えますが、実はつながっています。場作りを通じてつながりや信頼関係ができて、それが地域の中での相談ベースの案件につながります。そのノウハウが企画やプロデュースに生かされ、場所自体が魅力化していきます。この循環を意識しながら一貫した取り組みを行っています」とコメントしてくださいました。
森山さんの活動の出発点は、東京のITベンチャーでの経験にあります。答えを「教えない」育成方針や不完全な情報提供により、夢や希望を持って社会に出た若者たちが心折れて退職していく状況を見て、これは社会にとって大きな損失だと感じたそうです。その中でも一握りの成果を出していたのは、社会課題解決の実践的な経験をしてきた人でした。森山さんは、若い人たちがそうした経験を広く積むことができれば、この理不尽を打破できるのではないかと考えていました。その後様々な紆余曲折を経て、ここ小高という地で地域再生に取り組むことになりました。
森山さんは最後に、「我々の活動は現時点で地域事例としては胸を張れるレベルまで来ていると思っています。ただ、収益を上げていくこと、雇用を増やして活動のスピードを上げることも必要ですし、多地域連携でノウハウを貯めながら他地域の良い所を取り入れることも行っていきたいです。私自身、人と関係性を作るのが上手ではないので、助けを求めながら次のステップを考えていきたいと思います。これからもよろしくお願いします」と話してくださいました。
アドバイザーコメント
平塚 弥生 氏(株式会社Coneru 代表取締役)

平塚さんは2018年、岐阜県大垣市のシャッター街が目立つ場所に、空き店舗を利用した岐阜県初のシェアキッチンをオープンしました。パティシエを目指す人々や、お菓子作りの技術を持っているものの、結婚や妊娠、子育てなどで仕事を続けられない人たちに活躍の場を提供したい、との思いがあったそうです。
平塚さんはシェアキッチンでの交流について、「料理を一緒に作ることで、参加者同士の距離が縮まります。調理が進むと会話も自然に盛り上がり、料理が完成する頃には、日常の悩みや愚痴を共有する場となります。特に親密度が低いからこそ、ちょっとした愚痴を言いやすくなり、心のガス抜きができるのがシェアキッチンの良さだと思います」とコメント。
平塚さんは、自治会での活動事例において「調理共食とは、みんなでご飯を作って食べることです。この取り組みを通じて、居住していない人たちも参加するようになり、関係人口が増えてきました。流しそうめんや芋煮会を開催することで、地域に縁のなかった人々が集まるようになっています。これからの発展や自治会内の動きがすごく楽しみだな、という風に思っています」と話してくださいました。
トークセッション

ここから、登壇者と参加者、ナビゲーターの原亮(エイチタス株式会社)を交えて、特定のお題にそって意見を述べ合うトークセッションが行われました。
公民館的な取り組みについて森山さんは、「僕は自己実現が必ずしも起業である必要はないと考えています。相談に来る方の大半は、趣味の延長で稼ぎ、やりがいを持って続けられる環境を望んでいます。そんな方々をサポートすることも重要です。」と話してくださいました。
平塚さんは、シェアキッチン利用者の変化について、「初期は飲食店やカフェを開業したい人が多かったですが、最近は本業を続けながらお菓子作りを楽しむ人が増えています。年齢層も高くなってきて、第二の人生として自己実現を目指す人が多くなっています」とコメントしてくださいました。
森山さんは、「収益がないと続かないのに、公設の公民館では営利事業ができません。私設公民館では柔軟に対応できるため、文化生活に必要な取り組みを続けることができます。このモデルが他の地域にも広がることのメリットがすごくあると思っています」と話してくださいました。
セッションでは、参加者から沢山の質問やコメントもあり、盛況のうちにトークセッションは終了となりました。
参考リンク
- • 一般社団法人オムスビ
- • 株式会社Coneru
会議概要
- 日時:2024年12月23日(月) 19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:40名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
