Cheer Up! ProjectVol.6シネマ・デ・アエルと考える地域の文化資本の明日~持続困難な地域で”次”を育む文化拠点であり続けるには? イベントレポート

岩手県沿岸部では、復興事業終了後の急速な人口減少や需要減が大きな課題となっています。そんな中、小さな市場では事業の持続が難しい「映画」を通じた新たな地域の文化資本づくりに取り組んでいるのが、宮古市のシネマ・デ・アエル プロジェクトです。
2016年に立ち上がったプロジェクトは、各地の有志をメンバーに、ユニークな運営スタイルで、震災に耐え残った築約200年の酒蔵をセルフリノベーションしたコミュニティーシアター「シネマ・デ・アエル」を設置。映画上映をはじめアート、音楽、舞台、食と農、伝統文化、防災教育、様々なプログラムを企画・提供してきました。現在は沿岸部のみならず、県外からも多くの人たちが訪れ、その名称が示す通り新たな”出会い”の場となっています。
シネマ・デ・アエルが目指すのは、事業が困難な地域でも持続・発展できる新たな文化資本の雛形となること。復興のフェーズを越え、人口減少に苦しむ地域で、かつては当たり前のように存在できた民間による文化事業の”次”を創造し、次世代にバトンを渡すためには、どのような役割や仕組み、連携、協働が必要とされるのでしょうか。
シネマ・デ・アエルでプロジェクトを仕掛けてきた有坂民夫さんと、近代都市史・近代建築史研究者である東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻都市デザイン研究室の玄田悠大さんを登壇者に迎え、参加者のみなさんと共に考えました。
挑戦者プレゼン
有坂 民夫 氏(シネマ・デ・アエル プロジェクト プロジェクトマネージャー)

「シネマ・デ・アエル」は東屋さんの蔵(旧酒造)に設置された文化交流空間です。2016年9月、岩手沿岸に位置する常設映画館「みやこシネマリーン」の閉館により、南北220キロの広範囲から常設映画館がなくなってしまいました。有坂さんは、閉館していく映画館をなんとかしたい、という思いで「みやこシン・シアター」プロジェクトを立ち上げ、新しい挑戦を始めます。新しい映画館は、「映画で遭える・映画と出会う」という意味を込めて、「シネマ・デ・アエル」という名前になりました。運営方法はユニークで、支配人やプログラムディレクターはおらず、それぞれ異なる背景を持ったメンバーがプログラムのオーナーとなり作品を選んで上映しています。
「シネマ・デ・アエル」は、映画だけに依存せず、本と映画の相性を考えた書店やアウトドアショップ、アートイベントなど、地域の方々との交流を深めることにより、豊かな映画体験を提供しています。雑誌「ブルータス」や「まちの個性派映画館」の特集に取り上げられるなど、様々な媒体で紹介されました。
有坂さんは、「少し、投げかけをさせてください。私たちは何とかやってきましたが、運営は簡単ではありません。限界に近づく街の映画館を続けることは厳しい状況です。
『シネマ・デ・アエル』では最新の映画や快適なシート、オンラインチケットなどの設備はありません。また、雇用や金銭的な見返りもなく、将来の見通しも不透明です。しかし、ここを面白いと感じてくれる人々や作り手が集まり、地域とつながる協力者の支えで続けています。私たちは、お金では買えない豊かな体験を提供する場として、自分たちができる範囲でやっています。このプロジェクトが将来どうなるかはわかりませんが、地域の文化資本としての役割を果たし続けるために、皆さんと一緒に考えていきたいと思います」と話してくださいました。
アドバイザーコメント
玄田 悠大 氏(独立行政法人国際交流基金 チーム長代理 / 東京大学 大学院工学系研究科都市工学専攻都市デザイン研究室 学術専門職員)

玄田さんは、日本と海外を文化交流でつなぎ日本の文化を海外に紹介し、都市の歴史や街づくりについて研究しています。
玄田さんと有坂さんが出会ったきっかけは、日本のミニシアターを紹介する "JFF+ INDEPENDENT CINEMA 2023" で「シネマ・デ・アエル」が取り上げられたことでした。ミニシアターは独立した小規模劇場で、2022年に日本で公開された映画のうち60%以上がミニシアターで上映されており、映画文化を支えていますが、ミニシアターの数は減少しています。
玄田さんは、「ミニシアターは、人が集まる場所であることが重要でしたが、中心市街地が空洞化することで減少してしまいました。現在、ミニシアターがどのような役割を果たしているのかを考えることが大事だと思います」と話してくださいました。
玄田さんは、街と映画館の関係性を歴史的視点から振り返りながら、映画文化と地域との関わり、ミニシアター文化の変遷、ミニシアターの現代性、そしてその空間が地域とどうつながっているかを紹介してくださいました。
トークセッション
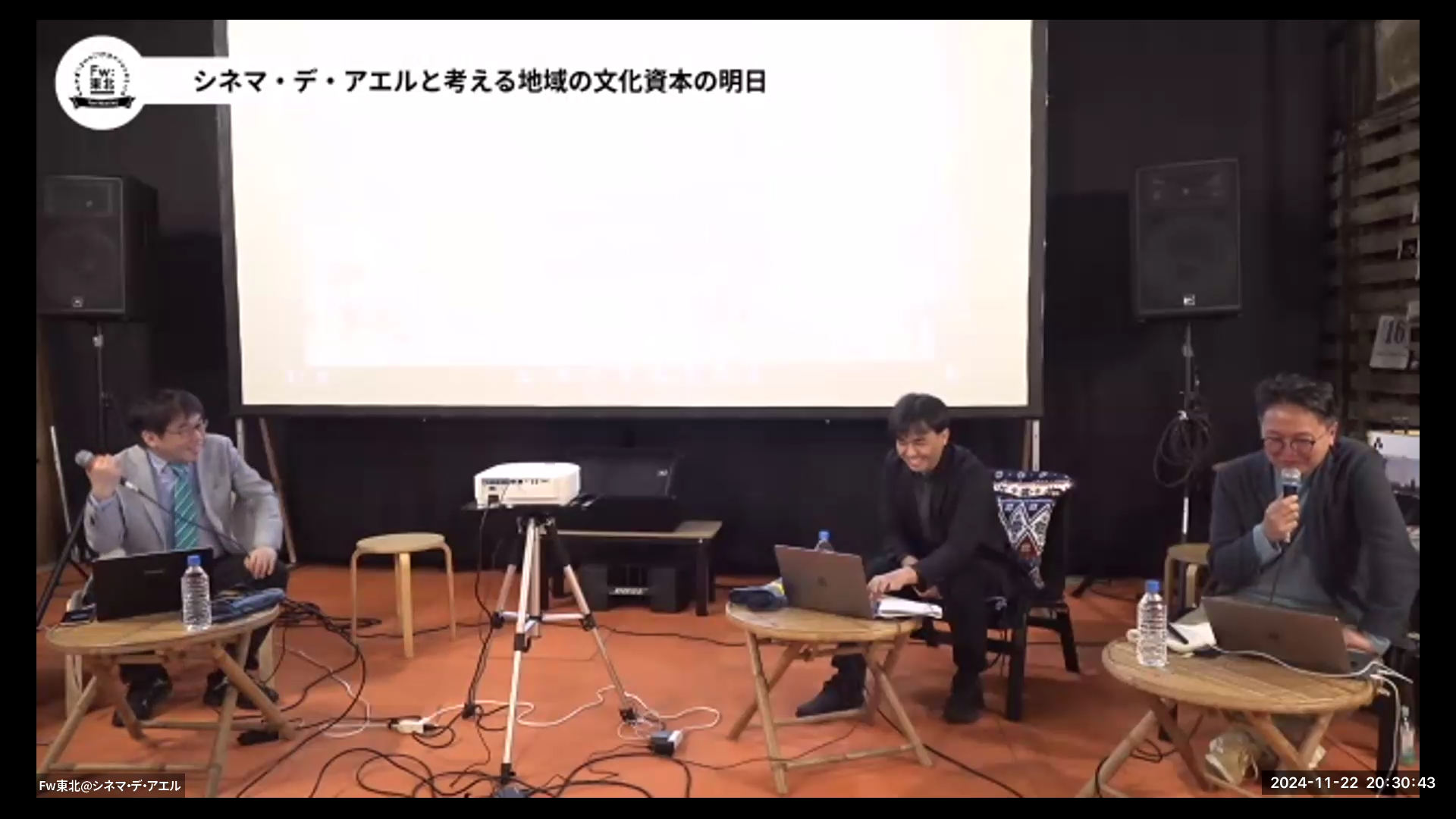
ここから、登壇者と参加者、ナビゲーターの原亮(エイチタス株式会社)を交えて、特定のお題にそって意見を述べ合うトークセッションが行われました。
セッションでは、玄田さんが、「シネマ・デ・アエル」のように酒蔵を活用した様々なリノベーション事例や、“DOCOMOMO Japan”選定建築物の事例を紹介してくださり、建物の利活用についての可能性が示唆されました。玄田さんは、「今の時代、専門家が建物の価値を考えて残してほしいと思っても、保存が難しくなってきています。重要なのは具体的な利活用方法や、建物に関わる人々の愛着度です。時代に応じて保存の方法やポイントが変わり、現在はこうした状況になり始めています。」とコメントしてくださいました。
有坂さんは、「僕らのスタイルのように専門家がいなくてもできるやり方があります。お金があまり儲からなくても、人生を台無しにしたり、借金まみれにならずにできる方法もあります。色々なやり方があるように、僕らの方法もその一つとして色々なところで実践してもらえると嬉しいです。」と話してくださいました。
今回のセッションでは、参加者から沢山の質問やコメントもあり、盛況のうちにトークセッションは終了となりました。
参考リンク
会議概要
- 日時:2024年11月22日(金) 19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:42名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
