Cheer Up! ProjectVol.5 陸前高田発 ワイナリーで世界基準のワインを目指す ~被災した若者がUターンで拓く地域の未来 開催 イベントレポート

高校生の頃に岩手県陸前高田市で東日本大震災に遭った及川恭平さんは、将来、地元で産業を起こして町の復興に貢献しようと決意し、2021年にUターンを果たしました。及川さんが注目したのは、地元の果樹栽培。リンゴやブドウの栽培が行われていた陸前高田で挑戦するために、ワインの道を選びます。ワインの専門商社への就職や海外のワイナリーでの住み込みなどの経験を経て、陸前高田に「ドメーヌミカヅキ」を設立します。
ドメーヌミカヅキは、畑と醸造所をもち、ブドウ栽培から醸造・熟成・瓶詰めまでを自分で行う“ドメーヌ”と呼ばれるスタイルのワイナリーで、及川さんは畑でのブドウ栽培からチャレンジを続けています。
被災した経験から、自分の道を探し出し、世界水準のワインを目指す大きな挑戦に踏み出した及川さんと、及川さんが織りなすワインを軸とした産業づくりに必要な応援とは何か。地域の風土や文化にも密接に絡むことができる、地域発のワインの可能性を拡げるべく、観光や食にも知見のある専門家も交え、全国のみなさんと考えました。
挑戦者プレゼン
及川 恭平 氏(ドメーヌミカヅキ 代表)
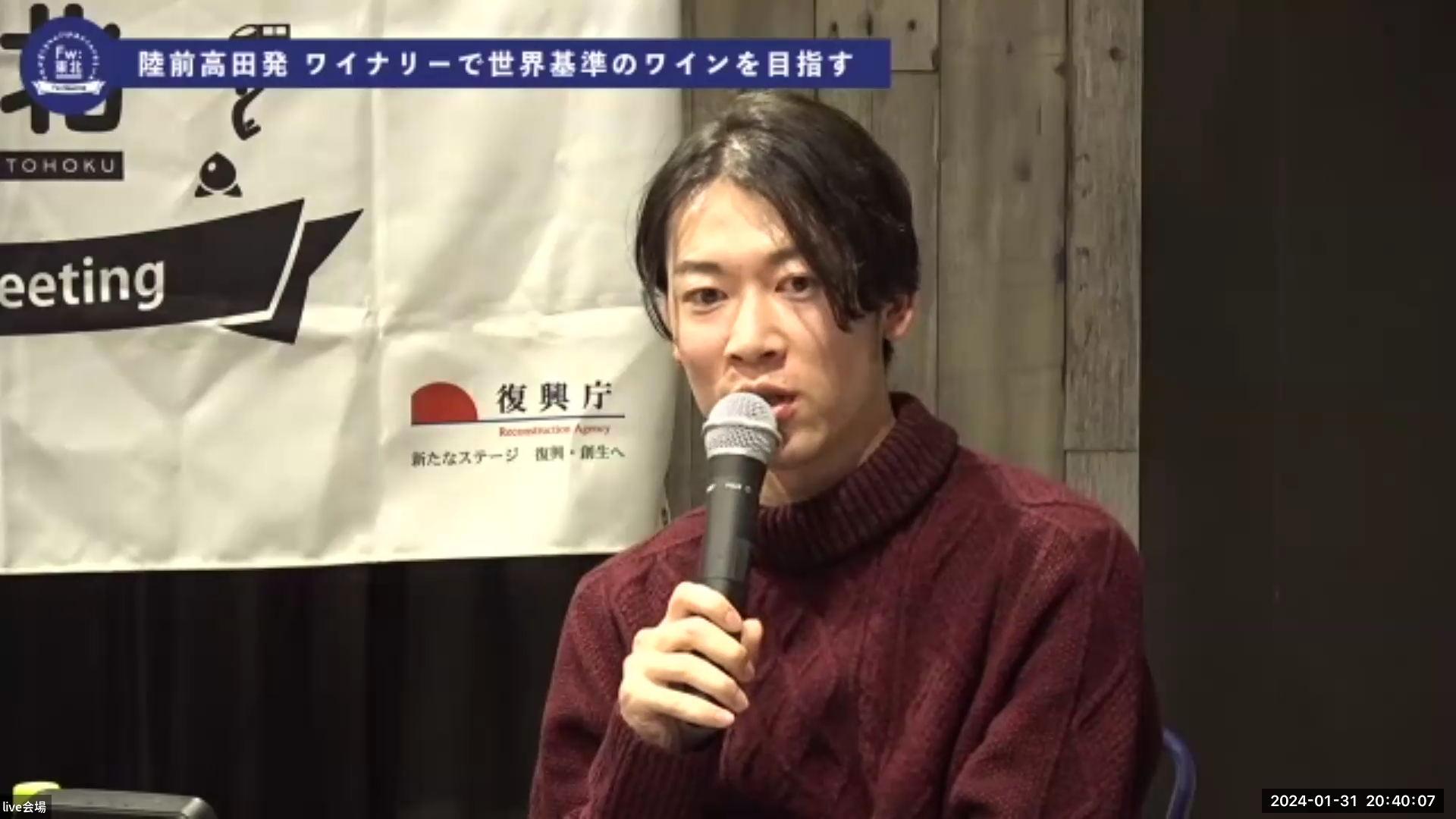
及川さんは、「人生のターニングポイントはやはり東日本大震災です。当時は高校2年生でした。自分が生き残ったのは何か意味があるのではないかと思い、地元に何か貢献できることはないかと考えました」と話します。その後、及川さんは、大学でフードサイエンスを学び、食に関する職業を選択しました。
及川さんは、ワイナリーの設立を目指しています。「街づくりという大枠の中でワイナリーがあると考えています。ワインを通じて様々なシナジー効果を生み出し、地域の資源を活用してコンテンツを作っていきたいです。現状認識をしながら、地形と歴史を活用した、真似できない街づくりを目指しています。地域の歴史ある果樹産業と農地も大切にしたいと思いますが、温暖化の影響でリンゴはどんどん作りづらくなっています。一方で陸前高田におけるブドウ栽培にとってはメリットが増えます。ブドウをワインにし、人々が街に留まるようにしたいです。また、ペアリングが生きるのがワインだと思います。海産物や寿司との結びつきを通じて、ワイン、農業、海産物などが一体化し、コンテンツとして成立すると思います。三陸でワイナリーを運営する意義を再考し、他と差別化した、尖ったワイナリーを設立したいです」と話してくださいました。
また、「なぜ陸前高田は全国的に珍しい沿岸の果樹産地なのか」を動画や写真を通して説明してくださいました。地理的特性(マイクロテロワール)や土壌など、環境要因が整っていることが示されました。
「ドメーヌミカヅキ」はコンセプトとして、月と海の満ち引きとかけています。及川さんは「アルバリーニョという、リアス海岸の気候風土にぴったりな品種のワイン作りを進める予定で、ミカヅキという名を冠する事で、シチュエーションや具体的なペアリングを提供できると思います」とのことでした。
及川さんは、「歴史を飲む」をテーマに、地域の産品と連携をしながら、「上下左右」の繋がりをつくるビジュアルイメージをもっています。先人の解明してきた地域のテロワールを活かして未来の人々に伝えていくこと、現代の人々とのつながりも重視して、点と点を繋げて線にし、それを面にして街として見せる必要だと感じているそうです。
最後に及川さんは、「2025年にワインをリリース予定です。過去にお世話になった人々がたくさんいるので、その人達から順にリリースしていきたいと思っています。礼儀を忘れずに、しっかりとした対応を心掛けます。そして、自社工場も2025年の夏頃に完成すると良いなと思っています。未来のまちづくりは、歴史を紐解くことで見えてくる、それが根底にあります。是非、応援していただけますと幸いです。よろしくお願いいたします」と語ってくださいました。
アドバイザーコメント
釼持 勝 氏(イーリゾート 代表)

釼持さんは、海外のワイナリー形態について紹介してくださいました。
「米国カリフォルニア州のナパとソノマは合わせて300以上のワイナリーがあり、カリフォルニア州でディズニーランドに次ぐ第二位の観光地です。ワイナリーを巡って歩く文化が根付いています。
海外と日本を比較した場合に大きく違うのが、テイスティングに対する取り組み方だと感じています。日本では大抵、『美味しいでしょ』という程度の説明ですが、きちんとした説明を行う事が重要だと思います。海外のワイナリーでは、ワインを比べてどのような違いがあるか、経年変化でどのように変わっていくか、などをきちんと教えてくれます。
また、成り立ちを含めたストーリーをはっきり明示しているワイナリーも多くなっています。中には、『私たちはストーリーだけが売り物だ』と主張するワイナリーもあります。そうしたワイナリーで話を聞き、その歴史、例えばイタリアから渡ってきた時の歴史などを聞きながら、ワインを作っている場所や樽を見て、納得し、共感し、商品を購入するということを行っています。この辺が、日本のワイナリーと大きく違うところだと感じています」
毛利 親房 氏(秋保ワイナリー 代表取締役/テロワージュ東北 代表)

毛利さんは、建築設計が本業で、東北の沿岸部や福島の原発の帰宅困難区域に自分の設計した建物がありました。震災後、変わり果てた街並みを見て、「何とかしないと復興できない」と思ったそうです。復興会議に参加した時に被災した漁師や農家の方と出会い、風評被害で物が売れないという話を聞きました。その中で、ワイナリーの設立というアイディアが生まれたそうです。
宮城県で唯一あったワイナリーが津波で流され、社長も亡くなり、宮城県のワイン産業が途絶えてしまいました。毛利さんは、ワインと食のマリアージュを通して食の応援や生産者の応援をしようと、2015年にワイナリーをスタートしました。
毛利さんは、ワイナリーの活動を通じて、「テロワージュ」というコンセプトを提唱しました。これは、フランス語の気候風土と人の営みを表すテロワールと、食とお酒を組み合わせたマリアージュというフランス語(結婚という意味)を組み合わせたものです。「テロワージュ」では、人と食と風景と文化を重視し、それぞれの地域の個性を表したロゴの作成も行っています。
「テロワージュ」の活動は、地域の魅力を国内外に発信し、多くの人たちに知ってもらうために、点から線へ、そして面へと展開していくことを目指しています。また、「テロワージュ」の活動は民間主導で進められており、予算の制約があるものの、生産者やシェフ、様々な地域の方々と協力しながら活動を進めています。
トークセッション
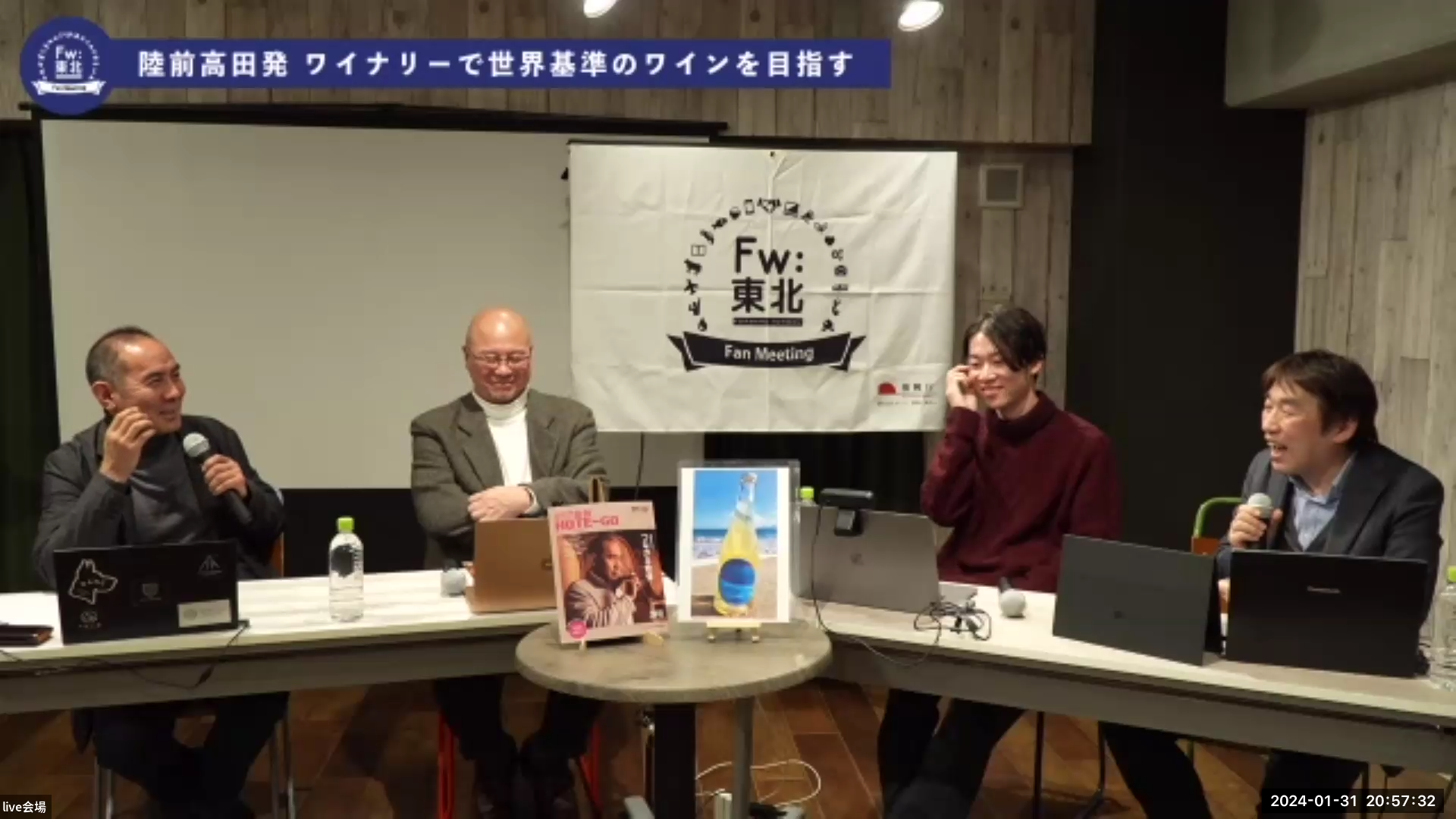
ここから、登壇者と参加者、ナビゲーターの原亮(エイチタス株式会社)も交えて、特定のお題にそって意見を述べ合うトークセッションが行われました。
ワイン作りにはどんな「ストーリー」や「物語性」が大切か、という質問が出されました。
及川さんは、「ワインにとって非常に大切なテーマが『持続可能性』です。環境に対する配慮(オーガニックやナチュラルな方法での生産)だけではなく、経営の『持続可能性』(収量の確保)も考える必要があります」と説明してくださいました。
毛利さんは、「ワイナリーの特徴を伝えるストーリーは、消費者が興味を持つ鍵になると思います。その地域ならではの特性、岩手県なら特徴的な土壌や地理的な位置などを強調することに可能性を感じます。『持続可能性』については、環境への負荷を減らすだけでなく、ワイナリーの経営自体を維持することも重要です。気候変動や物価上昇などの影響を受けやすい農業において、持続可能な経営を行うためには、適切な営業戦略や販売戦略が大切だと思います。及川さんには、ワインを通じて地域の魅力を発信し、活躍していただきたいです」とコメントしてくださいました。
「ワインと寿司のペアリング」という話題でもトークが展開されました。及川さんは、「三陸にイタリアンやフレンチの人材は中々いないですが、寿司の職人はいるのでガストロノミーツーリズムを行うことが可能です。外国人も喜びますし、その土地特有の新鮮なネタがあると、東京で食べるお寿司と差別化できます。そして、寿司とワインの合わせ方を説明できるとペアリングをアトラクションのように楽しんでもらえると思います」と指摘されました。
釼持さんは、「しっかり説明すれば単価が高くても売れるように変わります。寿司とワインの取り合わせは良くて、苦手な人でも醤油の中にワインを一滴だけ垂らすとか、オリーブオイルを使用すると寿司が食べやすくなったという例があります」と紹介してくださいました。
毛利さんは、「今年の目標は仙台市内の寿司屋さんにワインとお寿司のペアリングを広めることです。寿司屋さんから、『美味しいとは思うけど、ワインをどのように合わせたらいいかわからない』という話も沢山聞いたので、ぜひ及川さんと仙台市内でワインメーカーズディナーを一緒に行いたいです。和食と日本のワインは本当に合うと感じていています。海外のワインは同じ品種でも主張が強すぎて和食の繊細な味が感じにくくなることがあります。日本のワインならではの楽しみは、おそらく海外の人たちにも響くと思います。」とコメントしてくださいました。
今回のイベントはワインに対して非常に関心のある参加者が集まり、盛況のうちにトークセッションは終了となりました。
参考リンク
会議概要
- 日時:2024年1月31日(水) 19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加人数:55名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
