Fw:東北Fan Meeting 2022 東北デジタル創生塾Vol.10 デジタル活用で再構築される市民参加のプロセス ~「まちづくり参加スペース釜石市版Decidim」の事例から考える イベントレポート

住民の声を地域の意思決定にいかに反映していくか。震災復興のプロセスで、多くの自治体が悩みながら、前進を試みてきたテーマです。対話を重ね、意思決定を繰り返してきた努力は、今後も続いていきます。
こうした努力に寄与できるものとして、“市民参加のためのデジタルプラットフォーム”のサービスが、世界中の都市で活用され始めています。スペインのバルセロナで誕生した「Decidim(ディシディム)」は、その代表例で、岩手県釜石市では、様々な市民の自由な参加と、情報発信・意見集約の双方向化を目的とし、オンライン上でアイデアを集める場として、「まちづくり参加スペース釜石市版Decidim」を2022年3月に立ち上げています。
対面の会議に合わせて、オンラインでも広く意見を集めることで、市民ニーズを的確に捉え、「ともに考え、ともに活動する」環境をつくり、「全市民参加でつくるまち」を推進していく釜石市の試みから、他地域が学べることはどのようなものなのでしょうか。
ゲストとして、釜石市役所からDX推進室の佐藤政弘氏、一般社団法人コード・フォー・ジャパンから「Decidim」のプロジェクトマネージャーを務める東健二郎氏、さらには、同じく「Decidim」を導入した福島県西会津町のCDOで、地域情報化アドバイザーの藤井靖史さんの3名を迎え、地域での意思決定のあり方や、その道具として、デジタルがどのように活用しうるのかを考えました。
インプットトーク
佐藤 政弘 氏(釜石市役所 総務企画部 総合政策課 DX推進室 主任)
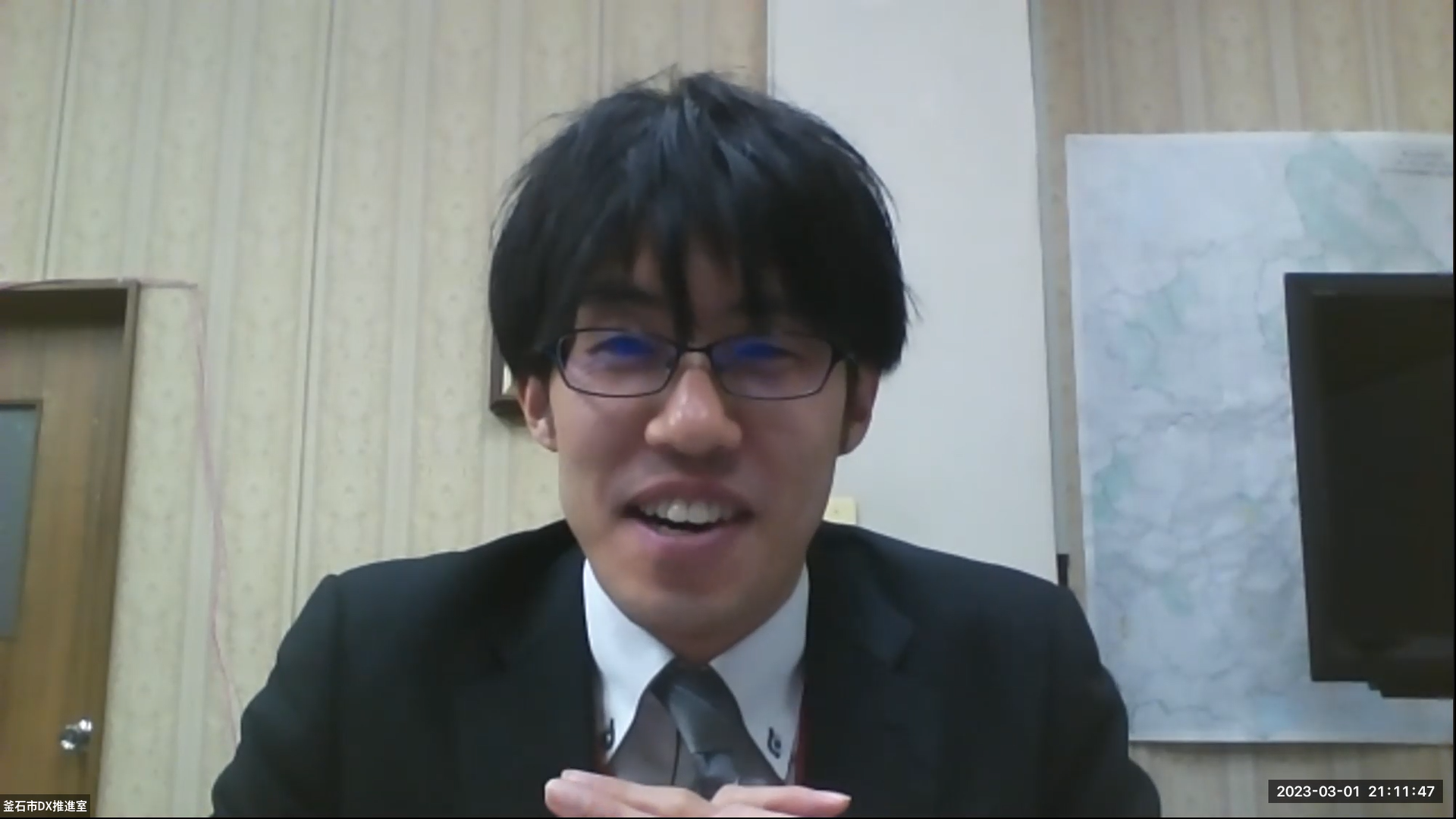
佐藤さんから、「全市民参加のまちづくりと釜石版Decidimの導入」についてお話をいただきました
釜石市は東日本大震災から10年が経過し、復興の完遂と新たなまちづくりの最高指針となる「第六次釜石市総合計画」を策定しました。これからのまちづくりは行政主導ではなく、多様な主体が主導で行う必要があることを実感し「全市民参加でつくるまち」という柱が加わりました。全市民参加に対する課題の解決法としてオンラインで議論をするツールDecidimを導入することになったそうです。
釜石版Decidimは「全市民参加のまちづくり~協働によるまちづくりの促進~」の考えをもとに、それぞれの持ち場での活動を継続しながら「ともに考え、ともに活動する」環境づくりを目指している、とのことでした。
一例として、「防災をみんなで考える取組」にアイデア投稿と「いいね投票」を行い、一番票を獲得したアイデアをさらに具体化して反映する事例が紹介されました。
最後に佐藤さんは、「釜石市は小さい町ですが、小さい町が一つ一つ頑張ってデジタルや地域まちづくりを進めるなら、日本全部が活性化してくるのではないか、との願いを込めて我々も頑張っております」と語ってくださいました。
東 健二郎 氏(一般社団法人コード・フォー・ジャパン GovTechチームリーダー/プロジェクトマネージャー)

東さんは「デジタル活用で再構築される市民参加のプロセス~市民エンゲージメントツールDecidim事例から~」というテーマで話してくださいました。
海外のDecidim事例として、Decidim誕生の地スペイン・バルセロナ、アメリカ・ニューヨーク、小規模都市のフィンランド・トゥースラ、中米のメキシコ・メキシコシティなどの活動が紹介されました。
日本のDecidimは2020年10月に兵庫県加古川市で初めて導入されました。これまでとは異なる層にアプローチするパブリックコメントのアップデート、公園などの公共空間について管理者と参加者利用ルールの整備・活用を共同して行うプレイスメイキング、地域運営組織での活用、デジタルシチズンシップなどの事例が紹介されました。また、日本のDecidimは民間企業による展開が多いのことも特徴だそうです。
様々な事例から、市民参加は「民主主義の筋トレ」であり、市民参加の文化を毎日コツコツ鍛えることが大切であること、市民参加のプロセスは、古くて新しい事柄で各国の取り組みを知ることができるという恩恵にもっと意識的になる必要があることが示唆されました。
東さんは、「日本もDecidimの色々な事例が生まれつつあります。皆さんもぜひ、お近くの自治体やグループでこうしたプロセスにどんどん参加いただくようになったらいいな、と思っています」とコメントしてくださいました。
藤井 靖史 氏(総務省 地域情報化アドバイザー、西会津町 CDO[最高デジタル責任者])

藤井さんから「地域住民の声を施策に」というテーマでお話をいただきました。
藤井さんは、デジタルを活用する前に、まちのビジョンや哲学を明確にすることが大切だと示唆されました。西会津町では半年以上かけてまちづくり計画の見直しを実施しました。その中でDecidimを使って意見を募集したそうです。地域外からの意見もあり秀逸な議論が行われた、とのことでした。
また、藤井さんは「日本のデジタルは15年遅れていると感じている、今までの自治体は小さなユーザーのニーズに応える『ロングテール』ができていない」と指摘されました。西会津町の事例が紹介されました。西会津町では、地元の中学生がDecidim を活用してフードロス問題や、高齢者の買い物にスクールバスを活用するアイデアを町へ提案し実践しました。会津バスの社長からコメントを貰い協力してもらったり、町の議会で取り上げられたりすることにより、自分たちの意見が無駄ではないことが実感でき、選挙の大切さや、政治家はどのように仕事をしているかを身近に感じて学べているそうです。
藤井さんは、「私たちは『民主主義をちゃんとやるにはどうしたら良いのだろう』を探求しています。Decidimの活用というのはこの中の一つの取り組みかなと思っております」と述べてくださいました。
登壇者・参加者のみなさんとのオンラインセッション

次に、ファシリテーターの原亮(エイチタス株式会社)を交え、登壇者・参加者とのトークセッションが行われました。
「釜石市では誰がDecidim導入を進めてきたか」
「Decidimを使うために必要な土壌とは」
「Decidimに参画する人を増やすためにはどうすればよいか」
など参加者の質問から活発な議論が展開されました。
セッションでは、中学生を含めた若い世代など、今まで意見を言う場がなかった人たちがDecidimで沢山の意見が交わされた事例が紹介されました。
また、Decidimは「拡声器」であり行政などの声の大きい人たちと同等の立場になれるようにエンパワーメントするもの、という考え方も話されました。
さらに、適切な意見交換のために町の現状を知るデータの重要性も示唆されました。
参加者からは、「皆さんのお話をお伺いして本当に良かった」「Decidimの仕組みがあるとすごく良いと思った」「デジタルを広げるにはアナログもしっかり行う必要も感じました」などの感想もあり、盛況のうちにセッション終了となりました。
参考リンク
- • 佐藤 政弘 氏(釜石市役所 総務企画部 総合政策課 DX推進室 主任)の資料はこちら
- • 東 健二郎 氏(一般社団法人コード・フォー・ジャパン GovTechチームリーダー/プロジェクトマネージャー)の資料はこちら
- • 福島県西会津町
会議概要
- 日時:2023年3月1日(水) 19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:76名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
