Fw:東北Fan Meeting 2022 東北デジタル創生塾Vol.4 めざせ移住促進!関係人口アイデア会議~地域と人の結びつきをデジタルで強めるには?イベントレポート

地域と域外の人の関わり方は、その地域に生活拠点を置く移住定住や多拠点生活から、観光やレジャーで訪れる交流人口、さらには様々な関わり方を含んだ呼び方である関係人口など、年々、多様化しています。
東北でも、首都圏などの他地域の人々が、沿岸部での震災復興活動のみならず、自分の興味関心に合わせ、地域へ足しげく通う場面も増えています。それにあわせて、地域の側では、そうした来訪者と関わるきっかけづくりとして、お試し移住や各種イベントが多数開催され、情報発信も頻繁に行われています。
移住促進を目指す地域では、こうしたきっかけで生まれる交流を移住の前段と捉え、関わり合いを増やすことが求められますが、そこでのデジタル活用にはまだまだ取組の余地が多く残されているようです。
今回の「東北デジタル創生塾」では、地域で移住促進のコーディネート役を担っている方や、関係人口の活動を担っている方などを対象に、域外の人たちとの関わり合いを濃くするためにインターネットなどのデジタルをいかに活用すべきかを考えるアイデア会議を開催しました。
ゲストには、観光情報学の分野の立ち上げにも寄与し、東北でも様々な実績を積んでいるイーリゾートの釼持勝氏や、地域SNSの研究でも知られている地域情報化アドバイザーの庄司昌彦氏、そして、「東北暮らし発見塾」でも連携しているソトコト・プラネットから事業ディレクターの中村崇さんをお迎えして、コーディネーターの方々のお悩みに答えながら、新たな活動を生み出す場となりました。
登壇者の紹介
釼持 勝 氏(イーリゾート 代表)

釼持氏は、主にスキー場業界に携わってこられ、観光事業歴は38年だそうです。
北海道ニセコ地域で外国人集客のきっかけづくりとなる人材育成を行われました。
自分のスタンスとして、あくまで地域の人材を育成することが大切。外から来たコンサルタントは長居をしてはいけない、という信念をもっている、とのことでした。
庄司 昌彦 氏(地域情報化アドバイザー)
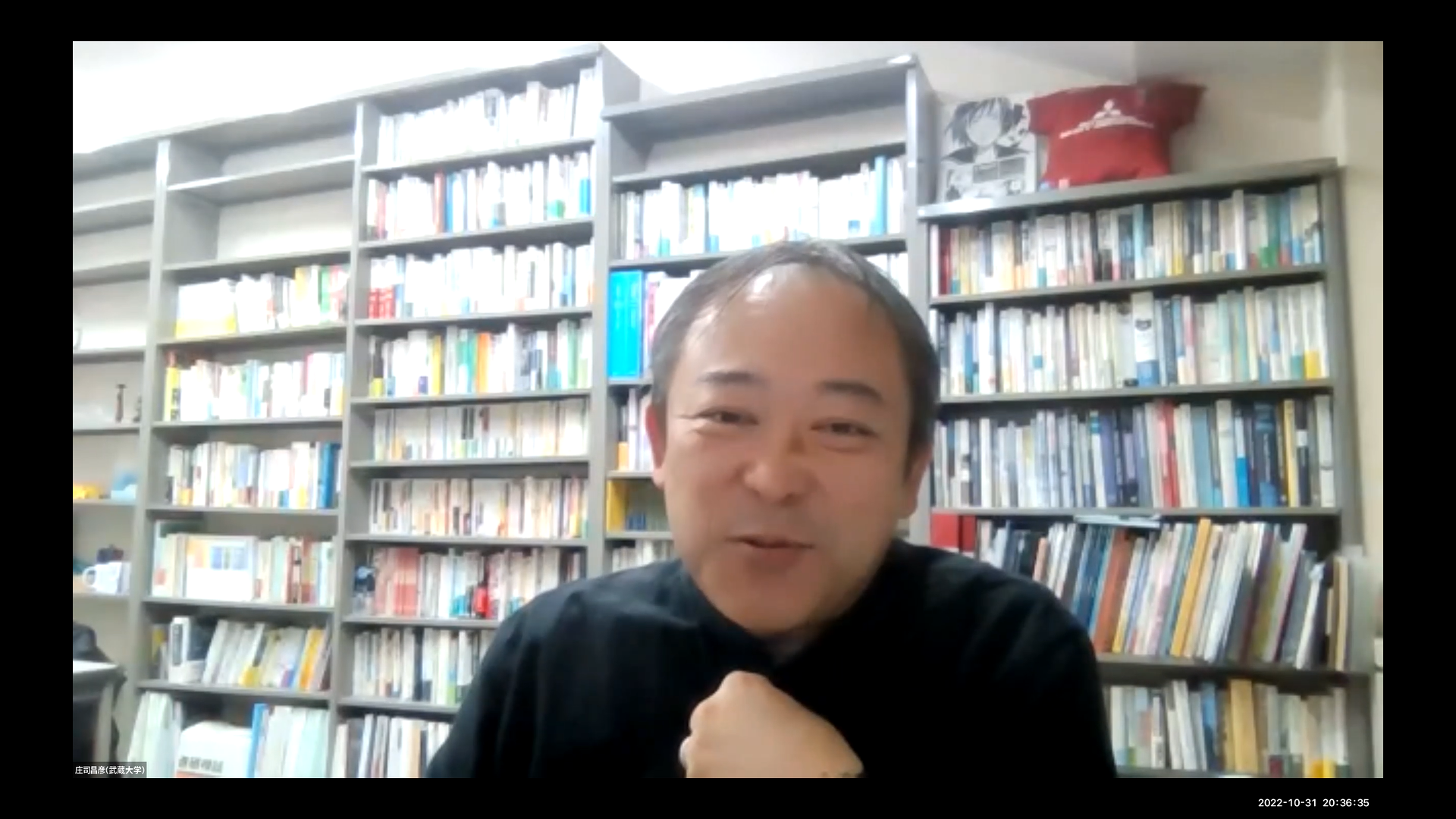
庄司氏はデジタル情報技術を使って地域を上手く回すための研究を20年行われています。地域情報化、地域SNS、オープンデータ、自治体DXに関する研究を行っていらっしゃいます。ご家族が秋田県出身であったり、仙台市の情報アドバイザーを行ったりしている等、個人としても東北に思い入れがあるとのことでした。
中村 崇 氏(ソトコト・プラネット 事業部 事業ディレクター)
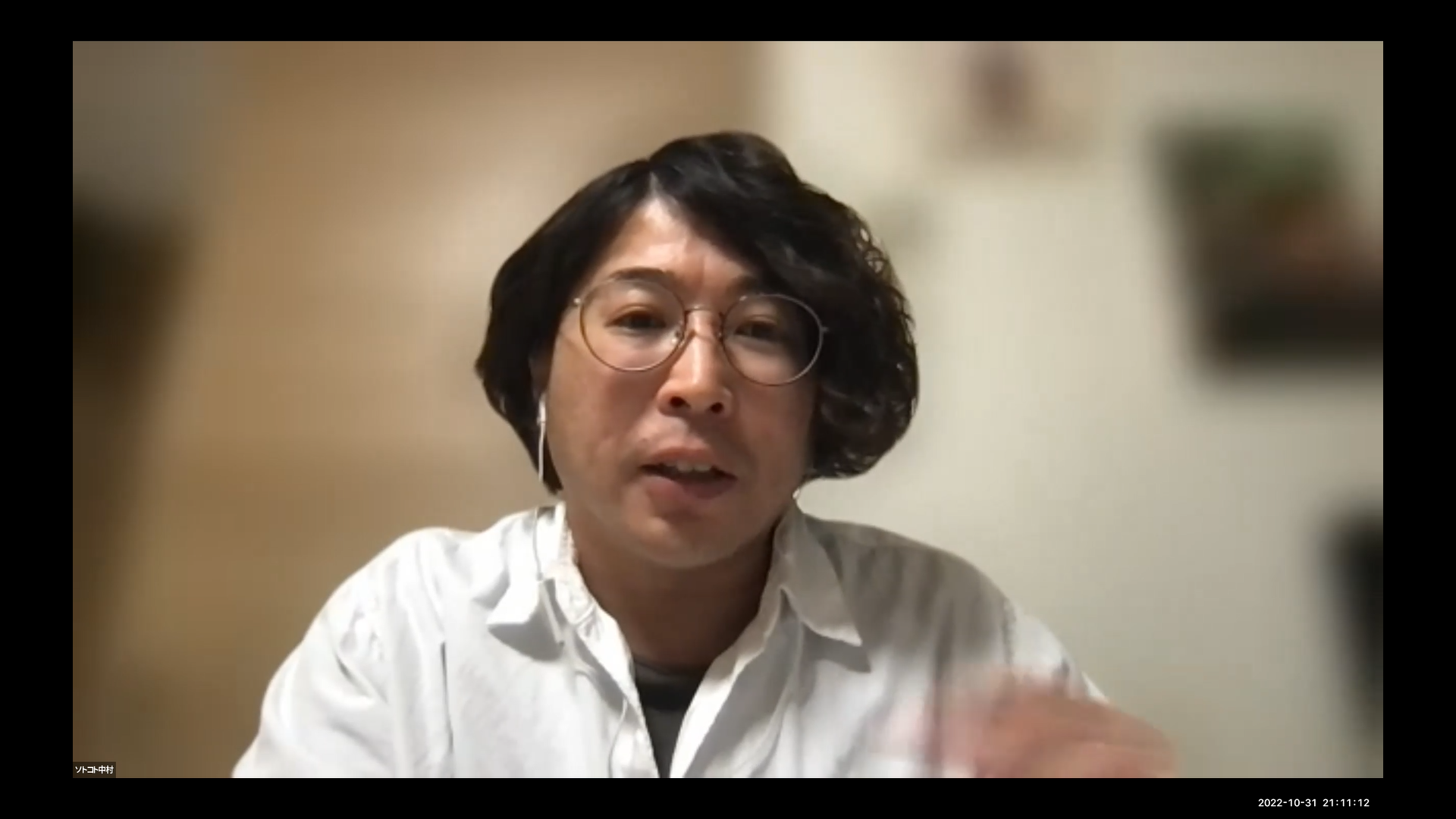
中村氏はソトコト・プラネット事業部で関係人口創出の講座運営を担当されています。東北とは福島県での講座やご家族の出身地であるという関わりがあるそうです。
ミニ・ブレインストーミング「移住促進・関係人口のお悩みブレスト」

移住促進や関係人口にまつわるお悩み(課題・欲求)を参加者から募集し、トークが行われました。
釼持さんは、現在のブランディング・マーケティングの基本として、まず調べて比較して判断する「認知」から始まるのではなく、たまたま訪れる、などの「訪問」から始まるフェーズがあることが近年の変化で、「認知」させることに拘らないほうが良いのではないか、と教えてくださいました。
庄司さんは「観光の売りは沢山あるが地域移住の売りがわからない」「観光で行きたいとは思うが住むとなると学校や仕事の問題がある」という悩みを取り上げられました。
中村さんは、「関係人口とは何か」という問いに対して、「定義があいまいなことが課題だと感じている。関係人口は、観光以上定住未満とも言われるが、食事や景色だけでは満足できない、地域の人と関わりたい人を含んでいる」と解説してくださいました。
続けて釼持さんが、観光における魅力が変化していることに触れ、「現在の観光では、の良い食事と宿を主な目的として旅行に行く傾向が強まっている。今はおいしい食事を目的として海外旅行をする時代であり、これまで地域の観光資源とされてきた神社仏閣や明治以降に再建されたお城などに、かつてほどの集客力がなくなっており、今でも残っているのは圧倒的な景色やモノくらいしかない。」と解説されました。東北の海産物は北海道にも負けない魅力的なものである一方、それを目的に訪れる人があまり増えていない実態があり、PRなどに工夫の余地があり、観光の目的を整理して見直す必要がある点を指摘されました。
また、宿泊施設におけるリピーター率は、地域の人や宿の人と話す時間と正比例して高まるという調査結果が出ている。話好きの人が東北には多いが、地域を好きになることはコミュニケーション量に正比例すると言えるのではないか、という示唆もありました。
庄司さんは、あるホテルで行われている勉強会について紹介され、寝食を共にして仲間づくりとなることから、その後もSNSでのつながりが続いているとのことでした。SNSを上手に取り込むのが有効だそうです。
現在のSNSは「バズる」「映える」など発信して拡散するツールになってきていて、双方向の「人と人のつながり・やりとり」が減っている傾向があるそうです。釼持さんは、オンラインでも濃いコミュニケーションをするために、Twitterでお客さんが投稿したエントリーをリツイートする手法を取っている企業が増えているとのことでした。
釼持さんは続けて、正しい広報がなされていない、という問題を取り上げられました。宣伝が「買ってください、これは良いですよ」と見せるのに対して、広報では「これは良さそうだ」と他の人が評価して認めるようになります。特に旅行業界では現在、インフルエンサーよりも友達や知人など身近な人の評価の方により信用度があり、影響力があるとのことでした。
庄司さんは関係消費についても取り上げられました。美味しいものを食べたいと思った時に、一番安いものや一番良いものではなくても、「○○さんが良いと言っていた、○○さんの地元だから」といった関係性を上手く使うことによって満足する、消費の可能性について説明されました。
中村さんは、地域の人口が3万人以上か3万人未満かにより、受け入れの雰囲気が違うと感じているそうです。人口数千人の過疎の町では、そこに行っただけで感謝され、いてくれるだけで良いと感じられるそうです。移住側の人も、自分の好きな事が実現できる場所と認識できるのでその後につながりやすいそうです。
釼持さんは地域で背伸びをした努力をすると良くないことを示され、「できることはできる、できないことはできないということをあらかじめお客さんに知らせることが大事」と説明をされました。都会の人は日常的に高水準の外食ができる環境にあるため、いまペンションでフランス料理を食べても感動はないそうです。「うちはこれしかできない」と地域の魅力をはっきり打ち出す方がわかりやすく、聞いていた以上の体験ができて満足できるそうです。
中村さんは、地域のニーズの見せ方にも触れ、「ITを盛り上げたい、と打ち出すとIT関係の人しかこなくなる。関わる余白を広げておくが大事なのではないか。安直に関係人口が担い手不足の解消と考えると失敗してしまう。現在はスキルマッチング要素が濃いかもしれない。お互いの自己実現という視点から再考する必要があるかもしれない」との意見を述べられました。
また、ソトコトでは観光案内所をもじって、地域のハブになる場所を関係案内所と呼んでいるそうです。そこは地域の外からの人と地域内で活動されている人がつながる場所であり、カフェやコワーキングスペースやゲストハウスのオーナーが、客と地域とつなげてくれる場となります。ある地域では「地域おこし協力隊」の人を関係案内所の担い手として、外部の情報発信が得意な人を雇用しているそうです。
庄司さんは、「意識の低い移住」として、やることがはっきりしていない移住も考えるべきじゃないかとの意見を述べられました。そのような人でもパワーや能力があり、きっかけがあれば行動を起こせる人たちであるため、学んでからの移住ではなく、学びに行きながら住んで遊ぶ、学びの誘致でも良いかもしれない、とアイデアを出してくださいました。
参加者からは、「偶然も移住の共通点の一つなのかな、と思った」「デジタルとリアルの融合の仕方の大切さを確認できた」「知人がいたので参加したが楽しかった」等の感想が寄せられました。
参考リンク
会議概要
- 日時:2022年10月31日(月)19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:24名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
