Fw:東北 Fan Meeting 東北暮らし発見塾(陸前高田校)~地域と関わる暮らしの楽しみ方イベントレポート

東北への移住をテーマとした「東北暮らし発見塾」、今回は「陸前高田校」として、陸前高田市を取り上げ、市長や移住者の話が聞けるオンラインイベントを開催しました。
地域と移住者で新しい協働を生み出し、アクティブに関われる町として、市長や移住者のみなさんが感じている陸前高田市の面白さはどこにあるのか。本イベントでは、戸羽太市長が地域の魅力について参加者のみなさんへ直接語りかけるほか、移住者たちの実体験に基づく生の声などを聞きだしながら、参加者のみなさん同士とも語り合える場となりました。
お招きする移住者として、精密機器メーカーの開発職から移住により市民交流の活動をはじめた山本健太さん(福岡県田川市出身)、結婚を機に移住して地域でのコミュニティ活動に従事している山本ひろみさん(長崎県大村市出身)、大学時代からの関わりで陸前高田市に移住し、防災伝承事業のディレクターを務める久保玲奈さん(東京都出身)、サラリーマンから漁師に転職し、牡蠣養殖やワカメ漁に取り組んでいる佐々木快昌さん(岩手県久慈市出身)、そして、移住促進のコーディネーター役として、昨年の Fw:東北 Fan Meeting に登壇した多勢(旧姓 髙橋)瞳さんもリピート登壇し、それぞれの移住体験から生の声をお伝えいただきました。
また、「社会や環境がよくなって、そしておもしろい」をテーマとした未来をつくる
SDGsマガジン「ソトコト」との連動企画として、同誌の指出編集長を迎え、陸前高田市への移住をリアルに掘り下げました。
インプットトーク
①陸前高田市長による地域の魅力・取り組み紹介
戸羽 太 氏(陸前高田市長)
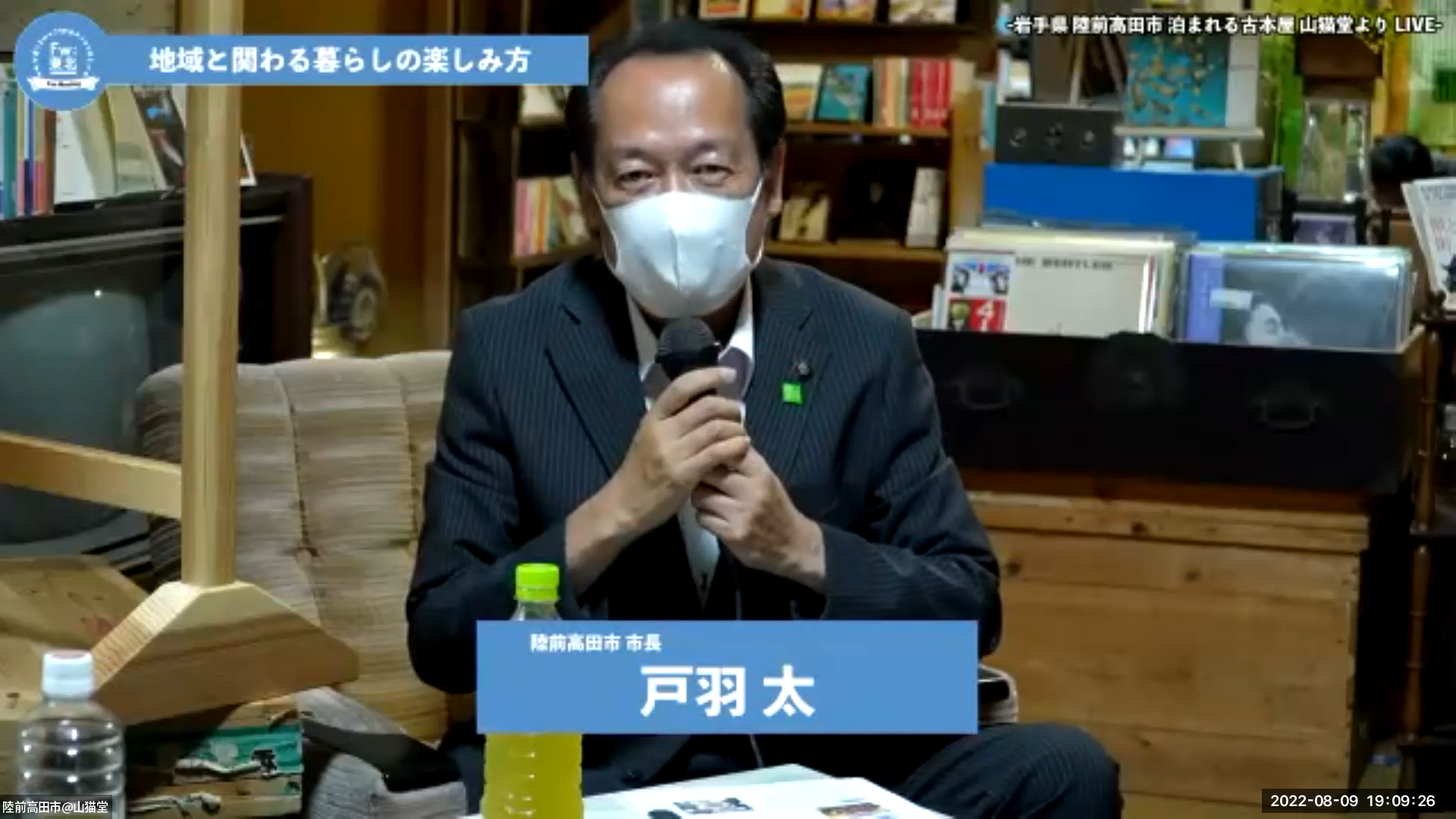
陸前高田市戸羽市長から地域の魅力・取り組みをお話いただきました。
震災支援を機に、様々な方々と知り合い、今も継続的に交流が続いていることが自分たちの地域の一番の特徴ではないか、と感じているそうです。交流人口の拡大として愛知県名古屋市、佐賀県武雄市、米国カリフォルニア州クレセントシティ、シンガポール共和国等、国内外で定期的に交流が行われているとのことです。
また、新しいものへのチャレンジと陸前高田市の良さをどのように残せるか、両立を目指してきたそうです。取り組みの一つとして「ノーマライゼーションという言葉のいらないまち」の実現を目指し、真の共生社会を作りたい、と想いを語ってくださいました。 陸前高田の一次産業について、取る漁業ではなく「育てる漁業」を行っている中、最高品質の牡蠣や陸前高田にしかない養殖技術のあるエゾイシカゲ貝、潮風を受けながら栽培する米崎りんご等が紹介されました。
最後に市長は「私自身も移住者ですが、外から来た人がしっかり地域の皆さんに受け入れて頂いていると思っています。移住を考えている方は、自分は地域に受け入れて貰えるだろうか、という心配があるかもしれませんが、陸前高田を理解して少しでも好きになっていただけばと思います」とコメントしてくださいました。
② 市長と指出氏との対談
指出 一正 氏(ソトコト編集長)
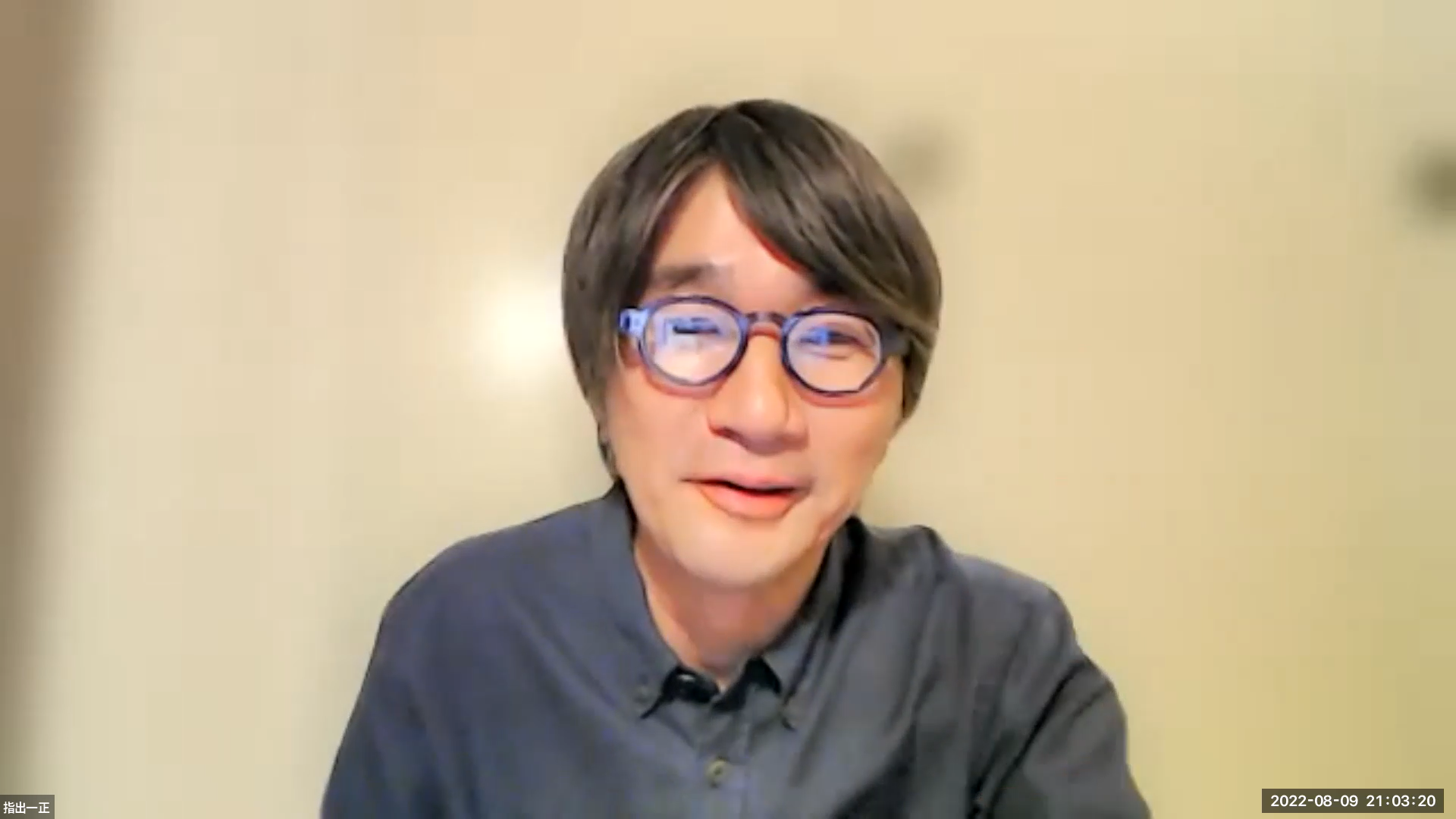
指出さんは、ノーマライゼーション共生社会について、次の世界のステップとして、誰もが幸せに生きることがとても大事になるので、その基盤が陸前高田で作られているとひしひしと感じたとのことでした。
市長はノーマライゼーションについて、自分育った東京では「障害のある人に対して手を差し伸べようという想いはあるけど喉元で止まっている人が多い」と感じていて、せめて田舎の町では障害のある人が自分らしく生きられる場所が必要だとずっと思っていたとのことでした。今は「きょうされん」(日本の障害のある人に対する支援をする事業所の連絡会)の全国大会でも市民の協力が沢山見られる等、市民の理解を頂いていると感じているそうです。
指出さんは、陸前高田とソーシャルビジネスについて、陸前高田で「育てる漁業」が広がっていることはまさにソーシャルビジネスであり、第一次産業は社会的課題を解決するためにこれから伸びていく可能性に満ち溢れている分野で、新しい視点でDXや福祉などを掛け合わせる等、元々あるものをどのように広げていくかが大切だと指摘されました。
市長は、東北は寒くて厳しいというイメージを持たれるが、夏の海水浴場やけんか七夕まつり、三陸花火大会など青空があって海があって笑顔がある。移住してくる若い人たちについても、スローライフで人間らしく生きている、一方でしっかり組織をつくり高齢者や相手の立場に立って色々なことを考えてくれていると感じているとのことでした。
移住経験・支援者の経験談
山本 健太 氏(一般社団法人トナリノ)
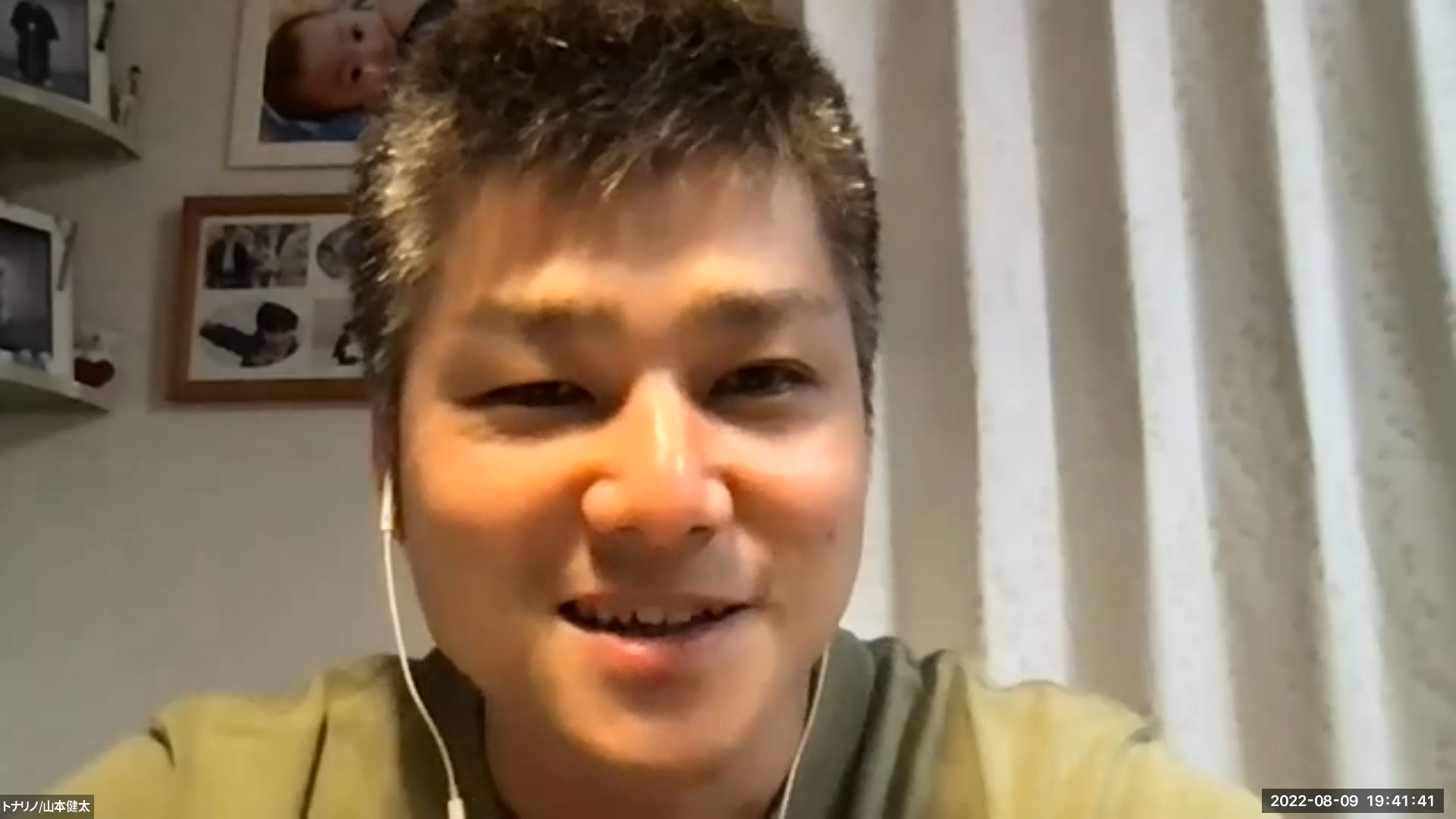
福岡県出身の山本さんは、精密機器メーカー就職後に東日本大震災を経験されました。山本さんはずっと機械と向き合う仕事をされていましたが、無機物より有機物とコミュニケーションがとりたいと思っていたそうです。震災ボランティアをきっかけに陸前高田の方と知り合い、2012年に移住されて今11年目とのことでした。
陸前高田に長期間滞在した時、地元の方が津波で流された自分の店の瓦礫を眺めながら語った「ここで歯を食いしばって生きていくしかない」という言葉に感銘を受けたそうです。ただお店を再開するお手伝いをするだけではなくて、自分がそこに身を置くことによって学べることが沢山あると語ってくださいました。
山本ひろみ 氏(一般社団法人トナリノ)
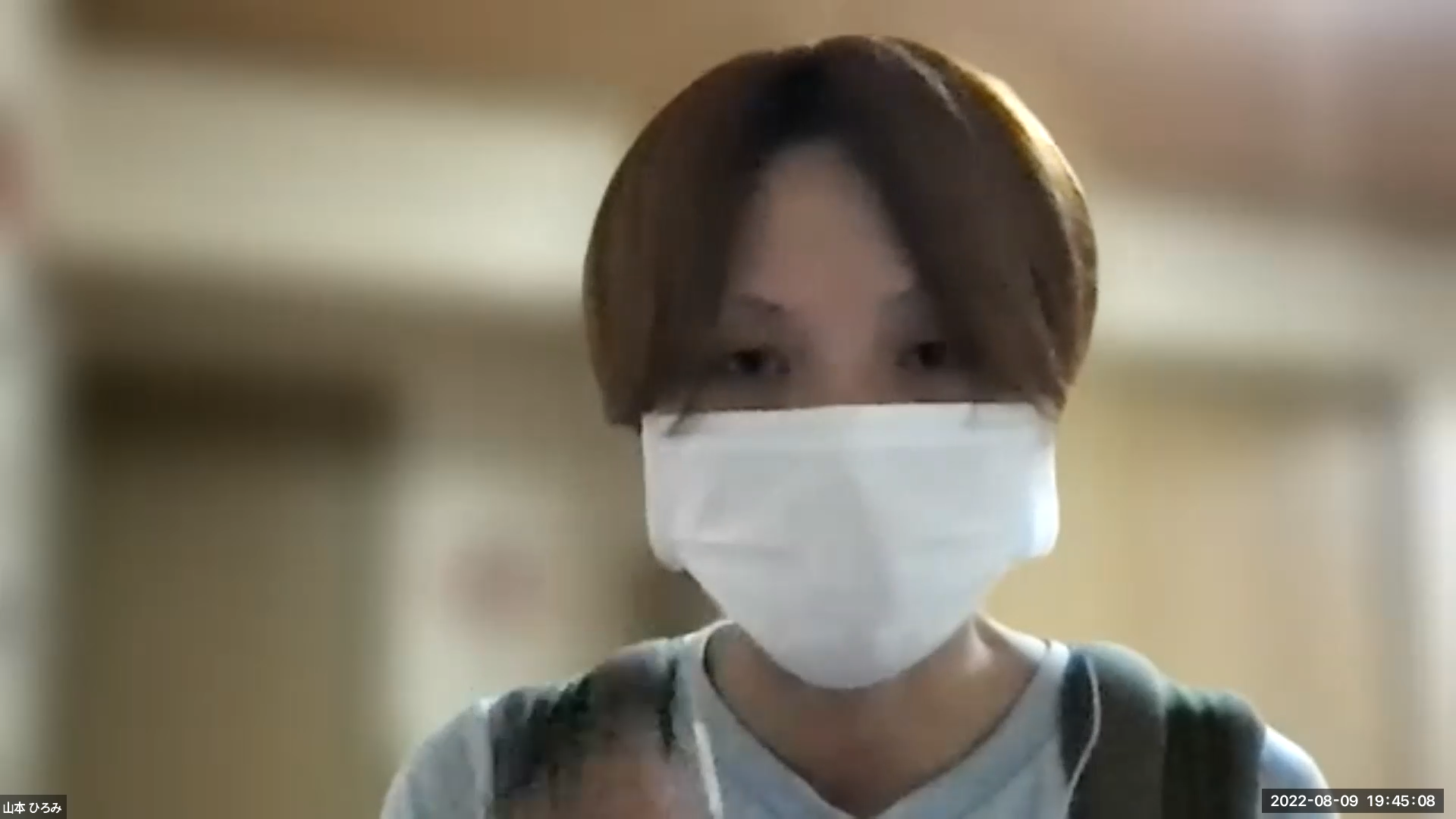
山本さんは、和歌山県に住んでいた時に東日本大震災が起きました。自分が居た場所は揺れもなかったので、テレビを見てこれが本当に現実に起きていることなのかと感じたそうです。約2年後、山本健太さんとの結婚を機に陸前高田へ移住されました。
トナリノではコミュニティを中心に、健康上の問題、コロナ禍などで人とのコミュニケーションが難しくなっている高齢者のケアや、子育て世代の移住者が孤独感を感じさせないようにする等、自身の経験や子育てに関することを活かした活動をされています。
久保 玲奈 氏(フリーランス)
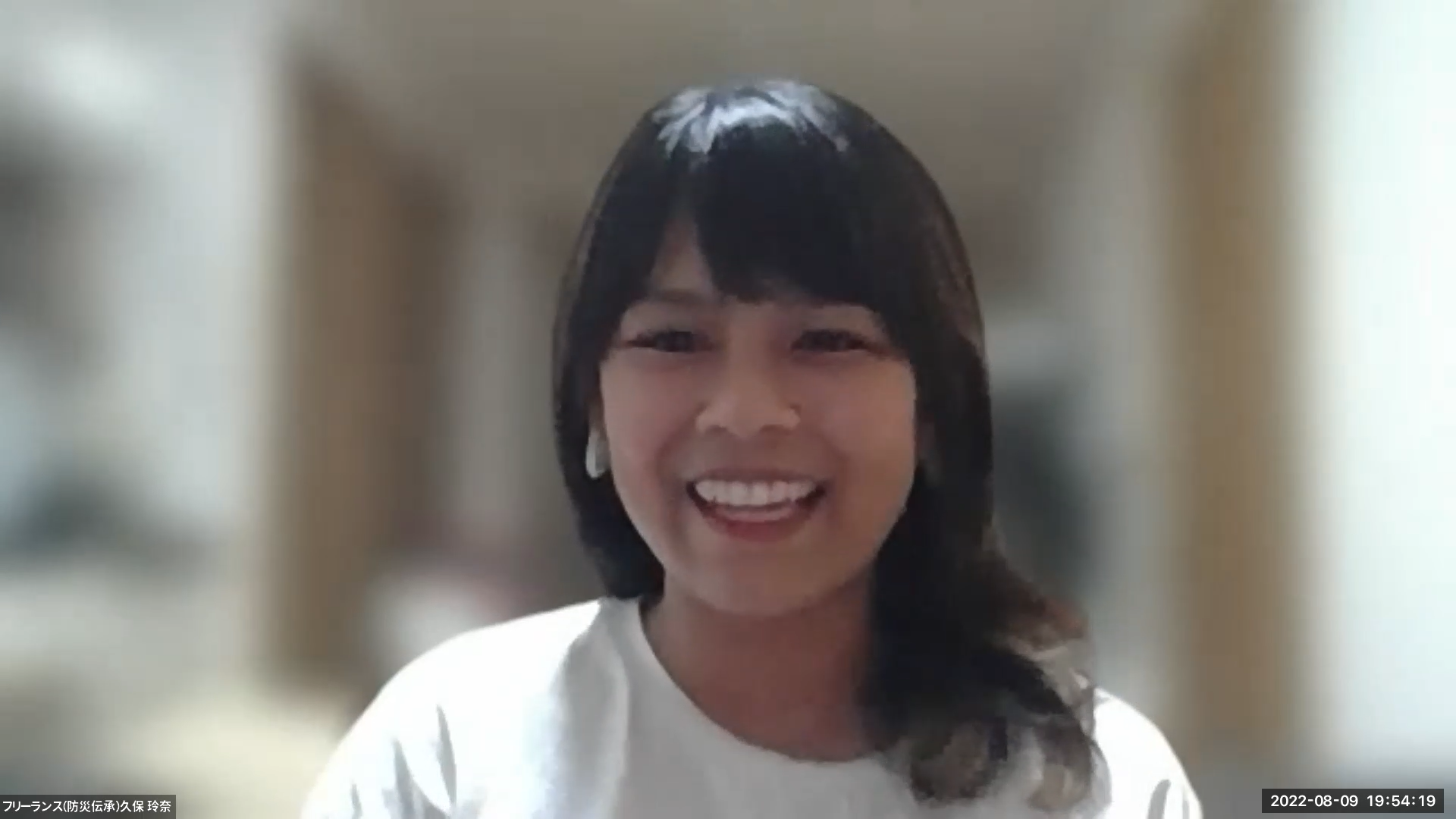
東京出身の久保さんは震災時、高校二年生でした。その後進学した大学で受けた建築学科の授業で被災した建築物の写真などを見た時に「今後建築の仕事をしていく上で自分の目で現地に見に行かないといけない」と思い、二泊三日のツアーに参加したことが陸前高田との最初の関わりだったそうです。そこで見た陸前高田の状況に強い印象を受け、自分になにかできることはないかとトナリノでのボランティアに参加され陸前高田に通うようになります。
久保さんは2018年に陸前高田に移住されましたが、建築の勉強をするために陸前高田を一度出て九州へ行かれます。そこでは、自分で思うようにはなかなか上手くいかなかったそうです。久保さんは、自分が本当にやりたいことをじっくり考えた中で、自分はなにかを「残す」ことに強い関心があると気づいたとのことでした。そしてフリーランスで防災を語り継ぐ仕事を行うことを決めたそうです。自分が頑張れる場所はどこなのかを考えた時に、色々な思い入れのある陸前高田が思い浮かび、もう一度戻ってきたとのことでした。
佐々木 快昌 氏(牡蠣漁師見習い兼ワカメ漁師)
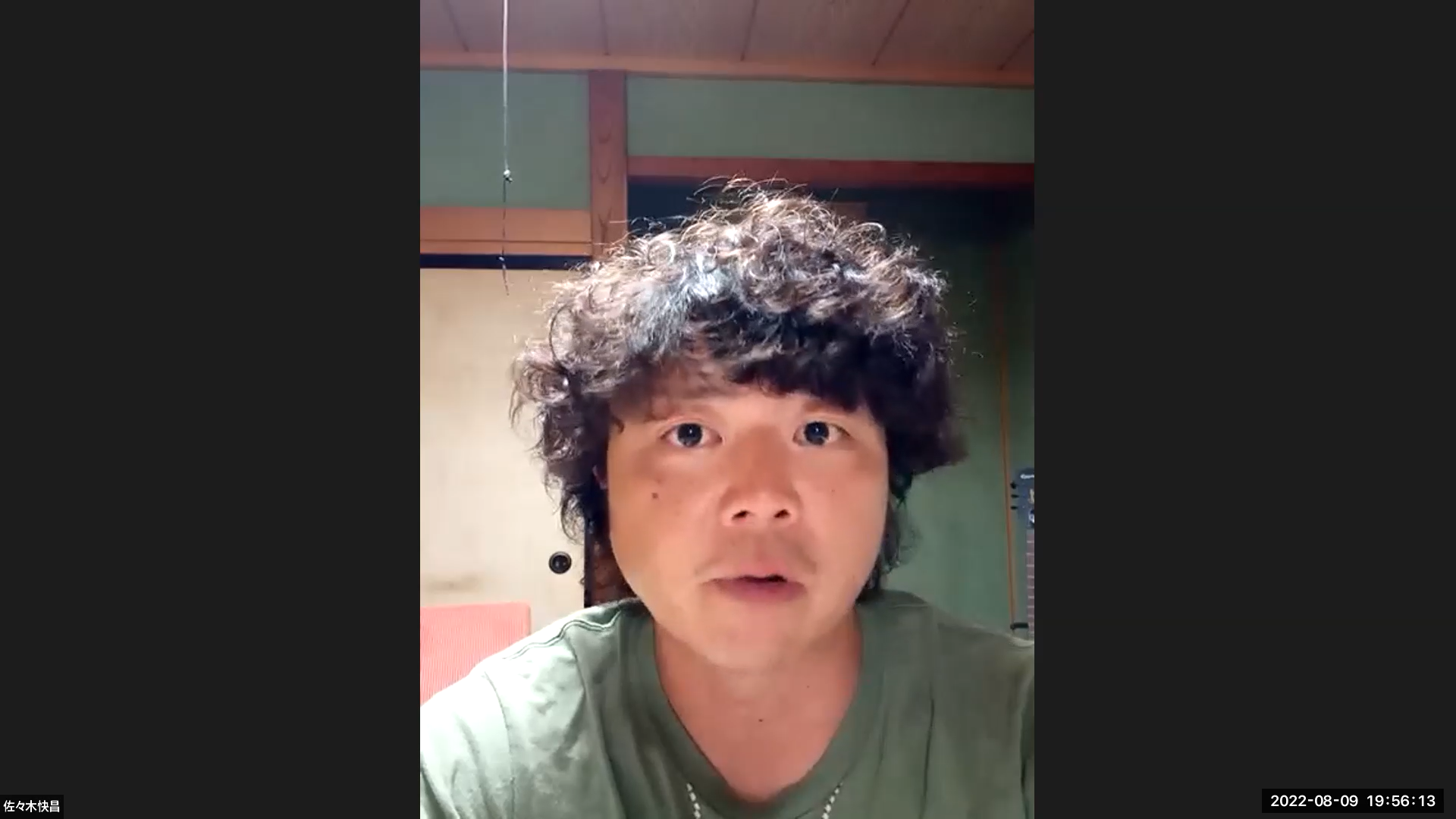
岩手県出身の佐々木さんは2019年に陸前高田に移住しました。移住のきっかけとして、震災後、自分は何か被災した人の助けができないか、何をしたら良いのかと悶々としていた時に、陸前高田に移住した高校の同級生から「下北沢で物産展をやるので一緒にボランティアをしないか」と誘いが来たそうです。そこで陸前高田の漁師や生産者と関わるようになり仲良くなっていったとのことでした。
佐々木さんは、震災後に中断されていた盆踊りの復活企画に参加されます。関東でサラリーマンとして仕事をしながら陸前高田に通うようになり、ずっと陸前高田のことを考えるようになっていったそうです。
佐々木さんは、自分の仕事や陸前高田について同級生に相談したところ「10年後に楽しいな、やってよかったなと思えることを想像して行動すればいいのではないか」とアドバイスを受けます。佐々木さんは「陸前高田に移住して漁業をやりたい、ボランティアの時に一番熱を入れていた牡蠣養殖を営む佐々木商店で働きたい」としか思えなかったそうです。そして弟子入りして漁師に転職されました。現在は独立してワカメ漁にも取り組んでおられます。
多勢 瞳 氏(特定非営利活動法人 高田暮舎)

千葉県出身の多勢さんは、転職を検討し始めた頃、当時のパートナーから地方移住することを提案されたそうです。コロナ禍だったのでオンラインで各自治体から地域の話を色々聞いて情報を集めたとのことでした。移住に向けて、自分の希望する地域おこし協力隊の募集があるか、なにかあったときに実家に帰れる距離か、人が合うか等を検討したところ、陸前高田に縁を感じたそうです。
そして、陸前高田のオンラインイベントに参加した時に「ありのまま、背伸びせず生きられそうな空気感」を移住者から感じて陸前高田の選考に応募されました。移住を考え始めてから三か月で移住することになったそうです。
多勢さんは現在、特定非営利活動法人高田暮舎で移住相談窓口、空き家バンクのマッチング、移住者同士の交流会、相談会などを行っておられます。
多勢さんは、陸前高田は自然豊かでイベントやコミュニティが多く、一人の人間として認識してもらえる、良い所が沢山あると感じている、と語ってくださいました。
参考リンク
- • 岩手県陸前高田市
- • 一般社団法人トナリノ
- • 特定非営利活動法人高田暮舎
会議概要
- 日時:2022年8月9日(火)19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:19名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
