Fw:東北 Fan Meeting Vol.7 「過去・現在・未来との対話を通じ、復興と“サステナビリティ”を考える〜持続可能な地域のために今私達に出来ること」

東日本大震災を契機として、人、アイデア、資金、政策など外部から多くのものが東北にもたらされました。内外の融合が、地域にこれまでなかった形の新しい連携や協働を生み出す一方で、過去幾度も津波被害に遭いながら変わらなかったものもあります。その最たるものが、「この土地に住み続ける」という三陸の人々の固い意志かもしれません。
今回のFw:東北Fan Meetingでは、震災を機に生まれ故郷である岩手県釜石市へのUターンを決意し、持続可能な地域の未来を創造することを目指して多岐に渡る活動を続ける株式会社かまいしDMCの久保竜太氏にお話を伺いました。久保さんは、2015年に釜石市の復興事業コーディネーターに着任以来、「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」の可能性を追求し、国内で初めて、持続可能な観光の国際基準・認証制度の地域実装を行いました。現在、ライフワークとして取り組むIwate, the Last Frontierでは、自己のアイデンティティやルーツに誇りを感じながら郷土で暮らし続けられる未来の創造を目指し活動しています。
また、他地域からは、出羽三山で知られる山形県鶴岡市から株式会社めぐるんの加藤丈晴氏をお招きし、ビジネスという手段を通じて、地域づくりへの市民参加を促すことで「幸せで持続可能な地域社会」の実現を目指す同社の取組を、羽黒山伏でもある加藤さんならではの視点からご紹介いただきました。
将来世代も「ここで生きていきたい」と思える持続可能な地域を実現するために、今私たちに出来ることは何か。ゲストのお二人による過去・現在・未来との対話を通じて、参加者の皆さんと考えました。
久保 竜太 氏(株式会社かまいしDMC サステナビリティ・コーディネーター/Iwate, the Last Frontier 共同代表)
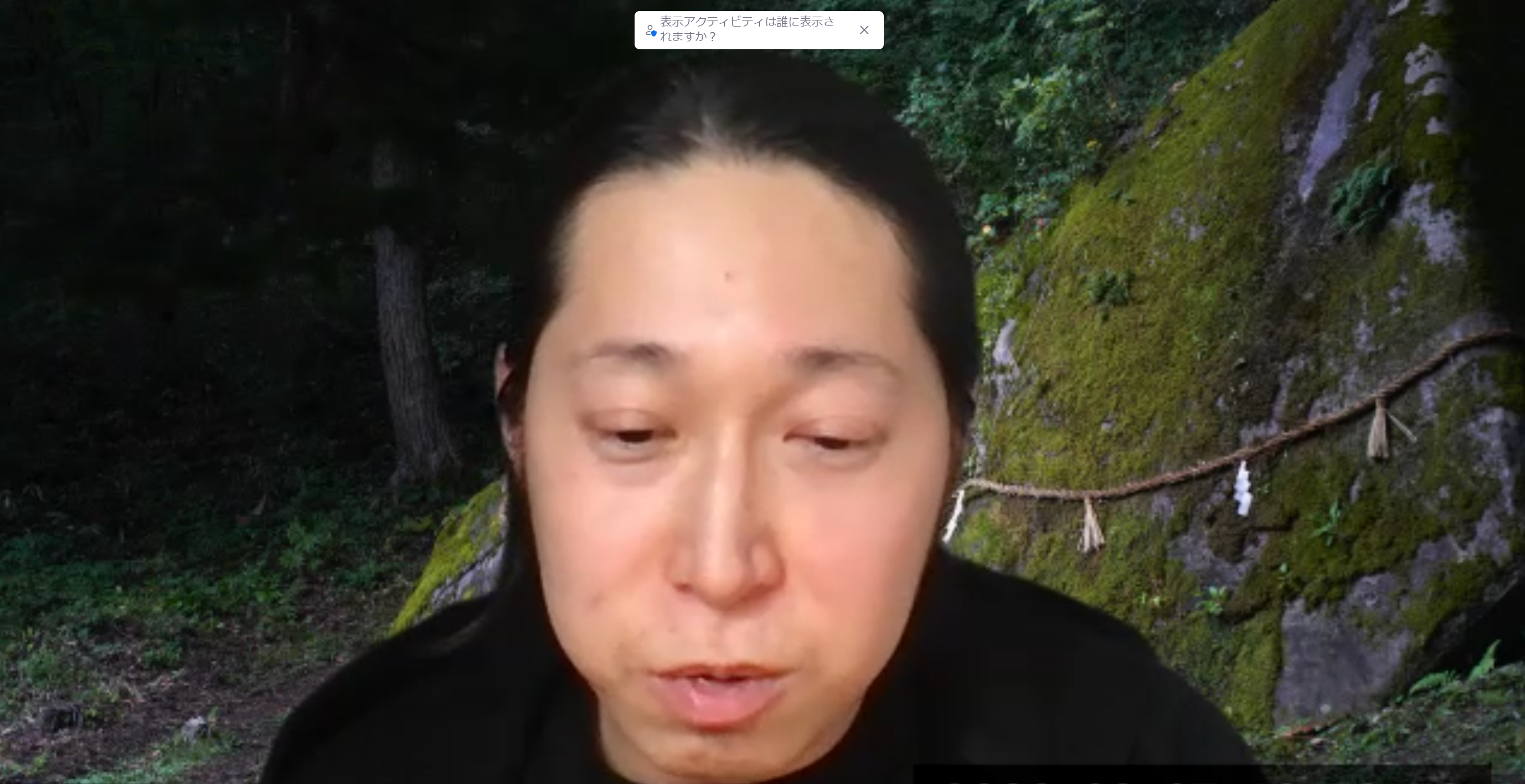
久保さんは、2015年に釜石市の復興事業コーディネーターとして着任され、「観光振興ビジョン」の策定や「持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)」などの実務を担ってこられました。
持続可能な観光の国際基準(GSTC)について教えていただきました。持続可能な観光には幅広い概念が含まれるので、どのような視点が必要かを因数分解したものが国際基準だそうです。国際基準に基づくサステナビリティ評価作業を行うことで、町の状態を客観的にデータ化し、より良いまちづくりを目指したい、とのことでした。
久保さんがサステナビリティの道を歩むようになった背景も教えていただきました。久保さんは、東日本大震災の翌日、家族の安否確認のため故郷である釜石市に向かわれました。10日間の滞在中、死を覚悟するような壮絶な経験をされ、人生観が大きく変わった、とコメントしてくださいました。
その後、書籍「三陸海岸大津波」から、三陸で繰り返されてきた津波の歴史を知り、「自分の先祖はなぜこの地で生き続けてきたのか、自分や子どもたちはなぜこの地に住み続けるのか」と自問するようになったそうです。 また、久保さんは、瓦礫の中で郷土芸能の「虎舞」を真剣に見ている町の人々の姿に、今までにない強い感情、「民族的アイデンティティ」が湧き上がったそうです。久保さんは東北の歴史を学び直し、「東北人とは何か」という問いに向き合うようになりました。
現在では、活動の一環として「Iwate,
the Last Frontierプロジェクト」を立ち上げ、岩手県の世界観を表現できるようなツアーの実施や、写真家のエバレット・ケネディ・ブラウン氏、漫画家の五十嵐大介氏等とのコラボイベントなどを行われています。
加藤 丈晴 氏(株式会社めぐるん 代表取締役/羽黒山伏(先達))
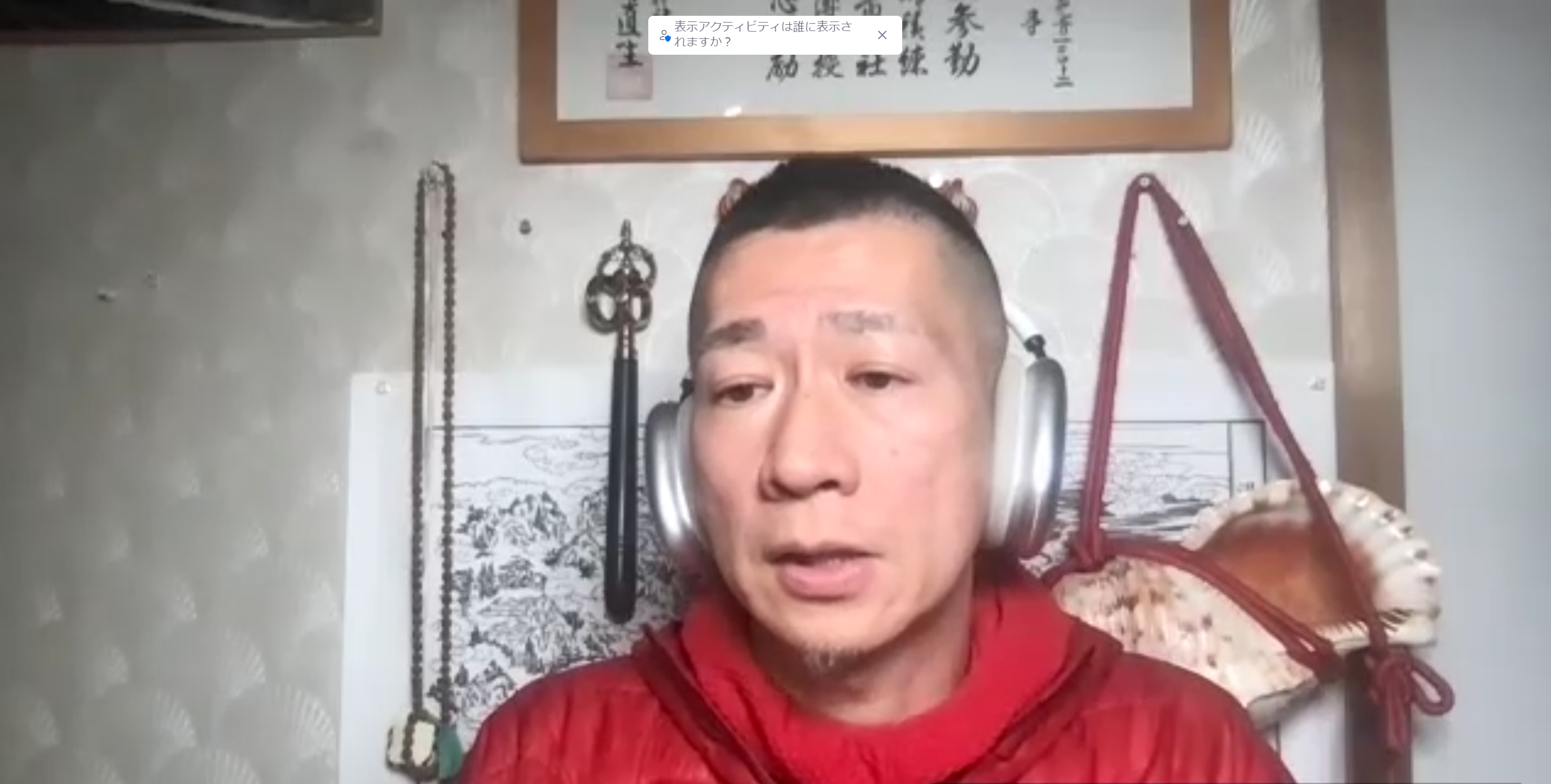
加藤さんは、東京の大手広告代理店で20年働いてこられました。山伏の星野先達(せんだつ)との出会いがきっかけで2011年に山形県に移住されます。現在、羽黒山伏として、海外から外国人を迎えての山伏修行体験 “Yamabushido” を提供する旅行会社を設立し、受け入れ活動を行っています。
山伏修行では、死と再生の山と言われている出羽三山を黙々と歩き、祈ります。修行中に発してよい言葉は、「承る」を意味する「うけたもう」だけです。その場に身を置いて感じることが大切、とのことでした。
加藤さんは、精神文化体験を通して、よりよい人生、日常、仕事に貢献できる場を提供すると同時に、事業を通じ地域の文化、自然、環境、社会経済が持続可能にできることを目指しているそうです。
SDGsとサステナブル・ツーリズムの違いはマネージメントだと指摘されました。国際認証の仕組みを利用して事業・地域を見直し、現代的価値に再解釈することが大切だ、とのことでした。
「自然と共に生きることが日本の文化であり、価値のあることである」という考えのもと、体験を提供することが、サステナブル・ツーリズムに求められていることだと感じているそうです。「今こそ生きる意味、命の大切さ、祈りの大切さが私たちに必要なのではないか」と語ってくださいました。
トークセッション

ファシリテーターの原亮(エイチタス株式会社)とインアウトバウンド仙台・松島の工藤氏を交えたトークセッションが行われました。
加藤さんは、今の活動を行うようになったきっかけを話してくださいました。リーマンショックの後、資本主義の世界で生き続けることに疑問を持ったそうです。目の前にある自然や人と付き合い、自分や子孫も幸せで、生が全うできる世の中の仕組みはないだろうか、と模索したそうです。その中で自分のルーツに近い自然の文化を実践しているのが山伏だった、とのことでした。星野先達の「あなたは目的がないとなにも出来ないのか」という言葉にも衝撃を受けたそうです。目標ありきの仕事をしてきた自分に、「頭ではなく体で考えること」の大切さを教えられた、とのことでした。
最後に工藤さんが、今後の展望を語ってくださいました。観光には「国の光を観る」という語源があるそうです。観光の定義を見直し、 “Tourism”や “Sightseeingではなく “Enlightenment” として東北から世界に発信していきたい、とのことでした。
登壇者と参加者との交流タイム
「時代の変化を感じた」「観光に対する考え方が変わった」「とても良い回に参加させていただいた」との意見が交わされました。
参考資料
- 久保 竜太 氏(株式会社かまいしDMCサステナビリティ・コーディネーター/Iwate, the Last Frontier 共同代表)の資料はこちら
- 加藤 丈晴 氏(株式会社めぐるん 代表取締役/羽黒山伏(先達))の資料はこちら
会議概要
- 日時:2022年3月7日(月)19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:33名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
