「ふるさとを離れ新たな発展に挑む伝統産業」イベントレポート

福島県浪江町で栄えた大堀相馬焼は、東日本大震災で産地が被害を受け、窯元数も激減するという存続の危機を迎えました。窯元も県内各地へ拠点が分散し、この10年間で、それぞれの移転先に定着していきました。
一方、2021年3月には、浪江町の復興のシンボルとして「道の駅なみえ」がグランドオープンを果たし、大堀相馬焼の展示販売や体験教室が設置されるなど、浪江町での活動拠点が機能し始めました。分散した地域に根付き、生業を続ける窯元の目線には、発祥の地の存在と自らの将来はどのように映っているのでしょうか。大堀相馬焼松永窯の松永武士さんにお話を伺いました。
他地域からは、同じく地域の伝統産業でありながら、発祥の地を離れて新天地での発展に挑む三千櫻酒造株式会社の山田耕司さんをお迎えしました。岐阜県中津川市で143年の歴史を重ねてきた三千櫻酒造は、蔵の老朽化と地球温暖化でこれまでの酒造りが困難となり、2020年に北海道東川町へ移転をし、公設民営型の酒蔵という新しい環境で酒造りへの挑戦をしました。
産地との密接な関係から品質やブランドを築いてきた伝統産業において、災害や温暖化など、産地そのもの危機に見舞われたとき、移転という道を進む奮闘を通して生まれた変化と進化とはどのようなものなのでしょうか。震災10年を迎えた大堀相馬焼と、昨年から新天地での挑戦をはじめた三千櫻酒造の例から、伝統産業の未来を考えるヒントを考えました。
松永武士氏(大堀相馬焼松永窯四代目/株式会社ガッチ代表取締役)インプットトーク

大堀相馬焼は、地元の誇り、アイデンティティともなっています。その中で、後継者問題や移転の必要性などが生じてきました。
後継者問題については、「地域おこし協力隊」の都市地域人材が、一定期間過疎地域に居住して地元の課題解決に取り組んでおり、浪江町では伝統産業の後継者として活動している事例があります。
「発祥の地」を離れての問題点、および新たに得られた点としては下記がありました。
- ・原料が放射能汚染で使えなくなる、という点については、原料や技法の自由さにつながり得る
- ・コミュニティとして、窯元が分散してしまった、という点については、様々な制約からの脱却、利便性となり得る
- ・土着性(風土)が薄れてしまった、という点については、純粋に商品力で勝負する、現場過剰主義からの脱却となり得る
今後については、現在の拠点に加えて、将来は浪江町にもう一度拠点を作りたいと考えていらっしゃるそうです。 作り手が足りないので育成が必要で、訓練校をつくりたいと構想しておられるそうです。
山田耕司氏(三千櫻酒造株式会社代表取締役)インプットトーク
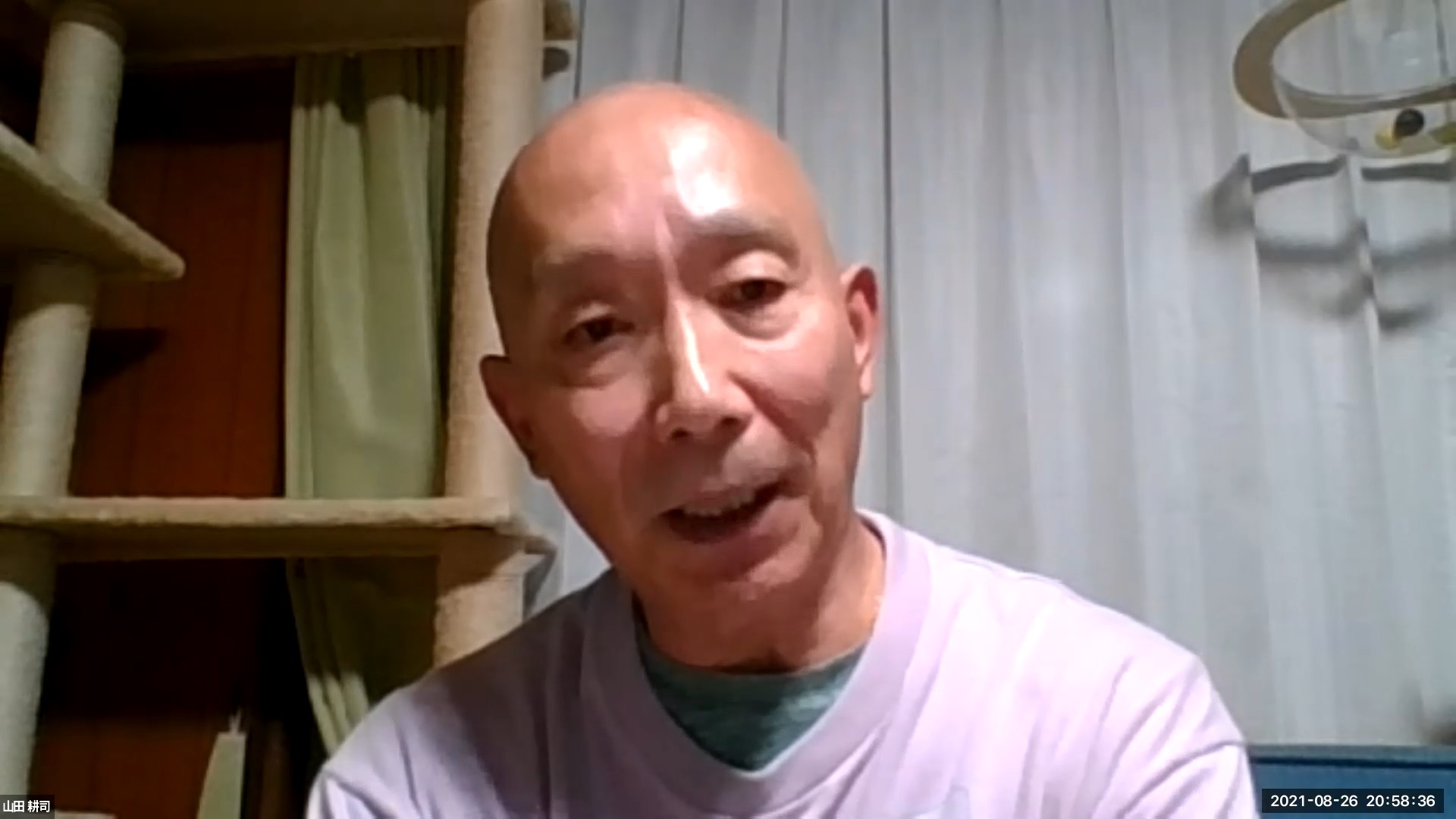
山田氏より、小規模日本酒造における今後の展開と展望についてお話をいただきました。
同社の抱えていた問題点としては、建物の老朽化、マーケットの縮小、気候の変化による管理業務の弊害などが挙げられるそうです。会社存続のために北海道に移転することを選択されました。
日本全国で見ると、後継者がいない酒造会社が増えているそうです。M&Aも一つの方法であり、地域に現存する酒蔵の維持には地域の応援が不可欠な反面、企業体でもあるために蔵元も努力する必要があると認識されています。
伝統を守るためには変化しなければならないこと、使命として現在の酒蔵で北海道の地元の人が酒造りをして経営に参画されることを希望しておられました。
トークセッション

ファシリテーターの原と登壇者によるトークセッションが行われました。 参加者から「異業種からの転身」についての意見や「ECをすることにより客層は変わったか」と言った質問が登壇者に投げかけられ、熱心な意見交換が行われました。
登壇者と参加者との交流タイム
参加者から「リアルな所がわかった」「人を育てる訓練校の必要性に共感した」「伝統をつないでいく人材の大切さ」などの感想なども聞かれ、盛況のうちに閉会となりました。
参考資料
会議概要
- 日時:2021年8月26日(木)19:30-21:30
- 形式:Zoomミーティングによるオンライン会議
- 参加者数:28名
- 主催:復興庁
- 企画運営:エイチタス株式会社
